テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。
歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。
※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています!(諸説ありでよろしくお願いいたします。)
源氏の衰退・平氏の時代が到来

1106年 平安時代後期 武家貴族 源氏は、白河法皇から東北の戦(後三年の役=1083年~1087年)で私戦(勝手な戦)を行ったとされ、冷遇を受けていました。
そんな逆風の中で、都の守護者として出世した源氏 当主 源義家(みなもとよしいえ)は、病にかかり亡くなります。
この時源氏当主を継ぐ立場の嫡男 義親(よしちか)は、九州や山陰等で朝廷に反抗していました。これは長く続いた源氏一門の冷遇への反発と考えられます。
さらに源義家の三男 義国(よしくに)は、都との関係を維持しながら東国に拠点を移し、東国武士の棟梁を目指していました。この義国の一族が後の武家の棟梁 足利氏です。
しかしこの頃、義国と常陸国の源義光(義家の弟)との間に勢力争いが起こり、これが源氏同士の戦に発展します。
そのため源氏一門 当主は、畿内にいた四男 源 義忠(みなもとよしただ)に継承されたのです。
一方 源義親の乱は、平氏一門の平正盛(たいらのまさもり)に制圧され、義親は誅殺されました。そしてこれ以降は平氏一門が都の治安維持を担うことになります。
そしてこれから平氏と源氏の明暗が分かれていきます。平氏当主の平正盛が出世する一方、源氏当主の源義忠は暗殺されてしまったのです。

この暗殺には諸説ありますが、前当主 義家と確執があった源 義綱(義家の弟)が、新当主の義忠からその座を奪おうとしたと考えらていれます。この事件を受け、義家の嫡男 義親の子である源 為義(ためよし)が新当主の座におさまります。
源 為義は朝廷の命により、暗殺犯 義綱を流罪にし、これで源氏一門の身内争いは幕を閉じたのです。
混迷する皇室
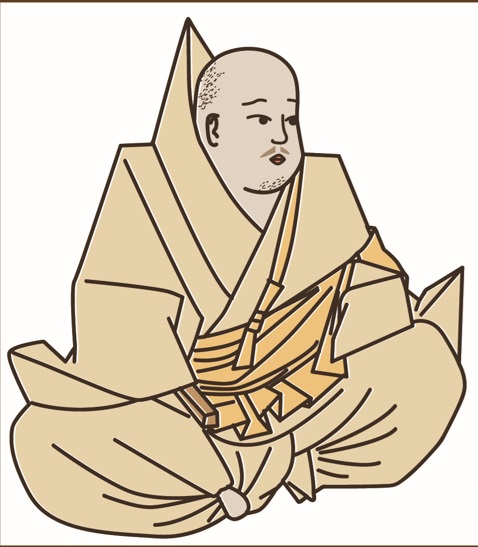
1123年 平安時代後期に、日本初の院政(天皇の父が幼年の天皇に代わり政治を行う)を開始した白河法皇は、未だ権力の座にありました。
白河法皇は養女の藤原璋子(待賢門院)を寵愛し、璋子を鳥羽天皇の妃にしました。そして二人に皇子(崇徳天皇)が誕生したのです。
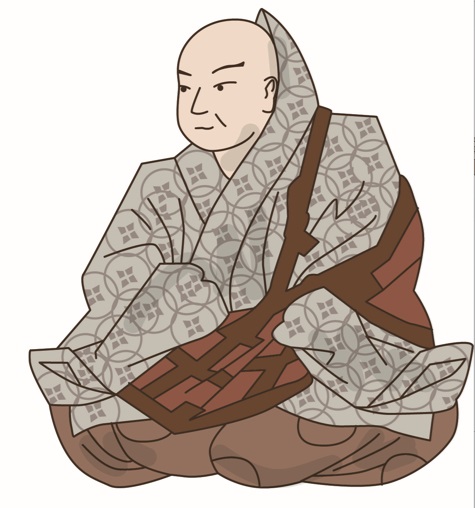


鳥羽上皇 崇徳天皇
そして時が過ぎ鳥羽天皇は譲位し、皇子(崇徳天皇)が即位され、長らく権力の座にいた白河法皇が崩御されます。すると鳥羽上皇は、これまでの白河政権の朝廷人事を一新し、自身の院政(鳥羽政権)を開始したのです。
そしてこの頃から鳥羽上皇と崇徳天皇の関係が悪化していきます。これは崇徳天皇に対し、藤原璋子(待賢門院)と白河法皇の不倫の子だとする嫌疑がかけられたからです。
これは貴族間の政争で流された噂がもとですが、鳥羽上皇はその噂(恐らく信憑性があった)を信じ、崇徳天皇・藤原璋子派は失墜したのです。
平氏による密貿易と繁栄
不穏になる朝廷政治、その一方で都を守護する平氏一門は、当主の平忠盛(たいらのただもり)が豪胆で武勇に優れた人物と評価され、九州の大宰府で日宋貿易(日本と宋(中国)との公的な貿易)に害をなす海賊を討伐し、一門の評価をさらに向上させていました。
そのうちに忠盛は、九州で朝廷を通さず私的に中国(宋)との密貿易を行うようになります。実のところこの頃、九州の商人と中国(宋)による民間貿易(密貿易)は盛んに行われていたのです。
日本からは主に金・水銀・硫黄・刀等が輸出され、中国(宋)からは宋銭・陶磁器・香料・織物・絵画等が輸入されていました。
忠盛はこの密貿易で珍しい品を輸入し、それを鳥羽上皇に献上することで自身の株を上げていたのです。
1132年 平忠盛は密貿易で得た資金を使い、鳥羽上皇のために得長寿院という御堂を建立し、千一体の仏像を寄進します。
これまでの功績により平忠盛は、武家貴族として初の清涼殿への昇殿(天皇の御殿に上がることができる特権)を許されます。
それからさらに時が流れ、1141年 崇徳天皇は鳥羽上皇の圧力を受けて譲位し、崇徳上皇の弟(近衛天皇)が即位します。これで崇徳上皇は(天皇が実子でないため)院政を行えない、権限のない存在となっていたのです。
1153年 平忠盛は公卿の大出世を目前にして亡くなります。しかし忠盛が築きあげた財力と人脈は、嫡男 平清盛(たいらのきよもり)に受け継がれたのです。
皇族・貴族による政争の始まり
1155年 近衛天皇が若くして崩御されます。しかしこの時近衛天皇には実子がいませんでした。
崇徳上皇はこの機に自身の皇子を皇位に付ける画策をしますが、鳥羽法皇の一存によって崇徳上皇の弟(後白河天皇)が即位されたのです。これで崇徳上皇の不遇な生活が続くことになりました。
これほどまで鳥羽法皇の崇徳上皇に対する憎悪が深かったのです。以降 鳥羽法皇と崇徳上皇の関係はさらに溝が深まっていくことになります。
同じ頃、最高貴族 藤原氏(摂関家)においても、家長の座を巡り争いが起こっていました。この当時の関白 忠通(ただみち)に実子がいなかったため、弟(頼長)を養子にして後継者としていました。
しかし関白 忠通に嫡男が生れ、弟(頼長)と実子どちらを後継者にするか、藤原氏(摂関家)が分裂します。この頃の都は多くの争いの種が育っていたのです。
地方に進出した源氏一門
都での争いをよそに、源氏当主 源為義(みなもとためよし)は都を離れ、九州や東国の地方豪族たちと争いながら力を付けていました。
しかしこのような為義の行いが粗暴とみなされ、後白河天皇と朝廷からの支持を失い、都で為義が出世する見込みはありませんでした。
そこで為義は東北の奥州藤原氏と縁戚になり、藤原氏(摂関家)に臣従してその権威を利用し、近江源氏佐々木氏や地方豪族たちを支配下にします。
為義は都で活躍する平氏とは違う道を選び、地方武士の棟梁になることを目指したのです。
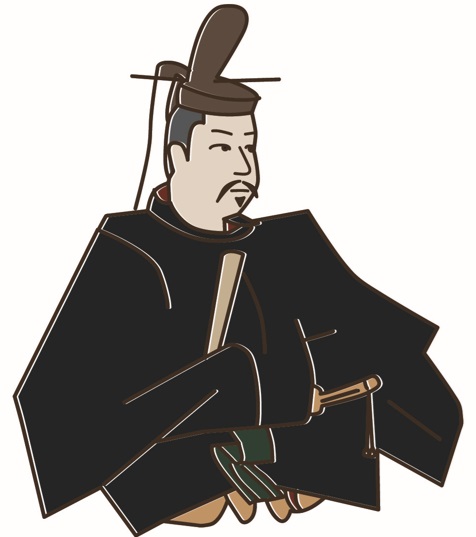
この頃、源為義の嫡男である源 義朝(みなもとよしとも)は、母方が後白河天皇の近臣者であり、為義に嫌われて廃嫡(相続する権利を廃すること)されていました。
そこで義朝は若いうちから京を離れ、東国に下向して東国平氏 上総氏に養育されて育ちました。そして元服後に東国平氏の三浦氏から妻を娶ったのです。
東国平氏(上総氏・三浦氏等)は平忠常の乱(1028年)で、西国平氏(平清盛の一族)と争い、それ以来多くの東国平氏は源氏一門との縁を繋いでいたのです。
源義朝は東国豪族の大庭氏や千葉氏を従え、勢力を築いていきます。そして新たな源氏の後継者 弟の義賢(よしかた)を討ち取ります。この時義賢の子の義仲(よしなか=後の木曽義仲)は信濃木曽谷へと逃れています。
義朝は東国で勢力を築いて京に上り、後白河天皇に仕える武家貴族になります。そして父為義や平氏と並ぶ武家貴族としての地位を固めたのです。
1156年 保元の乱勃発
源氏一門の分裂が決定的になる出来事が起こります。最高権力者 鳥羽法皇が病に倒れたことで、これまでギリギリ保たれていた京の勢力バランスが崩壊したのです。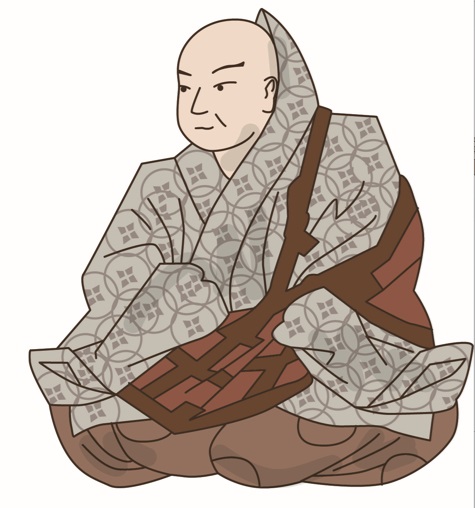
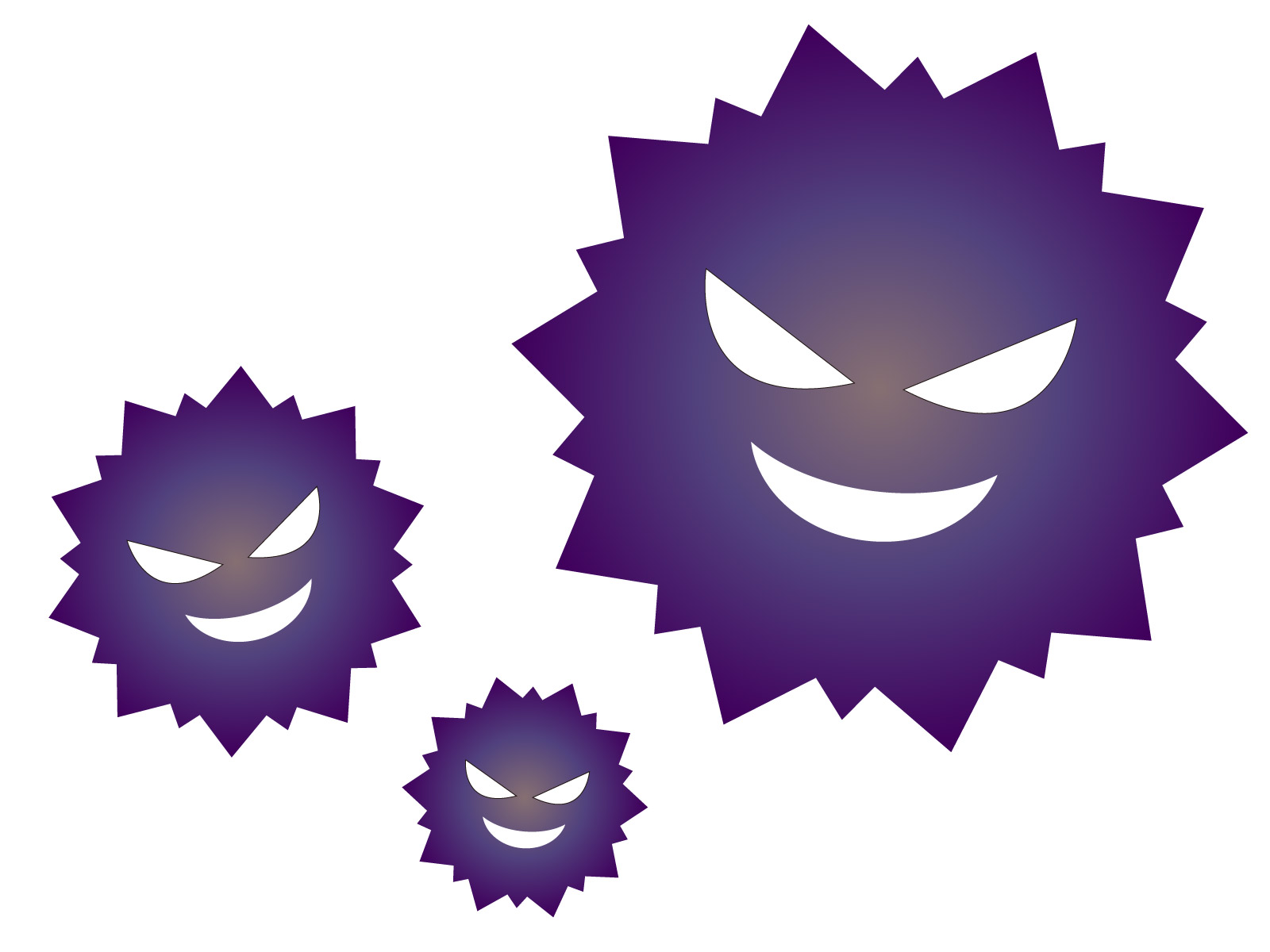
鳥羽法皇
崇徳上皇は鳥羽法皇の見舞いに訪れますが、面会は許されませんでした。
鳥羽法皇は崩御され、後白河天皇派(関白藤原忠通・源義朝・平清盛)、崇徳上皇派(関白忠通の弟(頼長)、それに臣従する源為義・平忠正(清盛の叔父))によって京の勢力は真っ二つになります。
そして保元の乱が始まったのです。
後白河天皇派は官軍となり、源義朝には東国源氏 足利義康、関東平氏(上総氏・千葉氏・三浦氏等)、そして畿内の源氏一門など、多くの武士が味方します。


後白河天皇 崇徳上皇
この戦で運命を分けたのが夜襲です。武家貴族として軍事に長けていた源為義と源義朝は、両者 夜襲を進言したのです。
この時崇徳上皇は奈良の援軍(興福寺等の寺社勢力)を待ち、その後決戦することを望み、一方後白河天皇は臣下に一任します。その結果義朝の夜襲攻撃が行われ、後白河天皇派が勝利したのです。
怨霊となった崇徳上皇

戦に敗れた崇徳上皇は、讃岐国に流刑になります。
讃岐国に着いた崇徳上皇は仏教に帰依(頼みとしてすがる事)します。そして讃岐国で大物主神を祀る、瀬戸内海の海上守護で信奉されていた、金毘羅大権現(現在の金刀比羅宮)に籠ります。崇徳上皇はここで保元の乱への反省の姿勢を見せ、京への帰還を願ったのです。
しかし後白河天皇の許しを得られないまま、京に戻ることはかないませんでした。後に崇徳上皇が崩御された後も許されずに無視され、とうとう崇徳上皇は都に災厄を起こす怨霊になったとされています。(日本三大怨霊 他には菅原道真・平将門)

この時に崇徳上皇を神霊として祀ったのが、崇徳上皇が帰依した金毘羅大権現(現在の金刀比羅宮)です。そのおかげで金毘羅大権現は神威(神の権威)を増したとされます。そして後の世では崇徳上皇は四国の守り神になったとする伝説が生まれるのです。
金刀比羅宮
香川県 琴平町の象頭山に鎮座する神社。御本宮は琴平山(別名「象頭山」)の中腹に鎮まり、 御祭神は大物主神と崇徳天皇です。古くは琴平神社、それから金毘羅大権現に改称され、現在は金刀比羅宮、通称〝こんぴらさん〟の相性で親しまれています。
祭神の大物主神は、出雲の国造りについて大国主命(おおくにぬしのみこと)に助言を行った偉大な神様とされ、農業・殖産・医薬・海上守護の神徳を持つとして信仰されています。
金刀比羅宮の境内の白峰神社に崇徳天皇が祀られています。朱塗(しゅぬり)で檜皮葺きの美しい建物です。
後白河上皇の院政
保元の乱において崇徳上皇に同意し国家を危うくした罪で、貴族(藤原氏)は流罪とされます。その一方武士(武家貴族)には厳しい処罰が待っていました。
この当時、政治犯の死刑というのはほとんどなかったのですが、武家貴族の源為義と平忠正は、同族の源義朝と平清盛の手により処刑されます。
源義朝は父(為義)と兄弟の死によって、名実ともに源氏一門の当主になるのです。しかし保元の乱で義朝の一族の多くが処刑されたため、源氏と平氏との力の差はさらに広がりました。
保元の乱での義朝の活躍は、東国武士の力が大きかった。そのことがあり義朝はさらなる勢力拡大を目指し、東国の有力貴族 藤原信頼(ふじわらのぶより)と結託するようになります。
藤原信頼は藤原氏(摂関家)の藤原道長の兄 道隆の一族で、摂関家本流の道長との政争で敗れたとはいえ、エリート貴族です。これにより源氏と藤原氏の関係が強化され、以後一蓮托生の関係になっていくのです。

1158年 後白河天皇は皇子(二条天皇)に譲位し院政を開始します。そして後白河政権には、二人の人物が台頭していました。
一人目は後白河上皇の養育係をつとめた信西(しんぜい)です。信西は貴族(藤原氏)の中では低い身分の(藤原南家)出身で、儒学に精通する学者です。
信西は出世が見込めず出家していところ、後白河上皇に才能を見込まれ、政権の中心人物になっていました。実のところ保元の乱での指揮と戦後処理は、信西が行っていたのです。
信西は儒学に通じ、君臣の義(君主と臣下は互いに慈しみの心で結ばれなくてはならない)を重要視し、皇族の権威を高めるために乱れた政治を正す徳政を行います。
まず信西は荘園(私有地)整理令を行い、皇族・貴族・大寺社が所有する荘園の管理制度を設けます。これは荘園を存続させるにあたり、天皇の認可が必要とする仕組みに変えたのです。
これで多くの土地が公領(国家の土地)なのか、または荘園(私有地)なのかの区別を付け、税の徴収を明確にできるようになりました。
また二条天皇の即位式を行うために、放置されていた内裏(天皇の儀式を行う宮殿)の復興をわずか一年で行い、皇室の権威を上昇させたのです。
一方信西とは別のルートで台頭していた人物が、藤原信頼(ふじわらのぶより)です。彼は後白河上皇の寵愛を受けつつ、源氏や平氏等の武家貴族と手を組み、主に軍事力で後白河政権の中心人物となっていました。
源氏と平氏の因縁の始まり
信西は後白河上皇の寵愛を受け出世する藤原信頼を警戒し、他の貴族からの反発を防ぐために、信頼の過度な出世を抑えます。しかしそれを恨んだ信頼は信西を敵視するようになるのです。
1159年 藤原信頼は後白河政権を主導する信西を打倒し、新たに二条政権を立ち上げるべく、二条天皇派として反旗を翻します。
この背景に親子でありながら後白河上皇と二条天皇の関係がよくなかったことがあります。もともと後白河上皇は政治への意欲が薄く、朝廷内では中継ぎの天皇と考えられ、早期に二条天皇に政権をつなぐ流れがありました。
しかし後白河上皇と信西は、院政を開始し主導権を渡さず、朝廷内でこれをよく思わない派閥が藤原信頼と結託していたのです。
藤原信頼は決起のタイミングを図り、当時中立の大勢力だった平清盛が、熊野詣(熊野三山へ参る事)に出かけた隙を狙い行動を開始します。
源義朝は藤原信頼と行動を共にしました。この時義朝は平氏との差を埋めるため、新たな二条政権に望みを託したのでしょう。

そして源義朝は信西がいる三条殿(上皇の住まい)を急襲し、屋敷を火の海にします。信西は逃亡を図りますが、ついに追い詰められ自害したのです。
これで信西一族は失脚、後白河政権は破綻し、後白河上皇は三条殿を脱出して弟が座主(住職最上位)を務めていた仁和寺に避難します。
一方反乱を知った平清盛は京へ引き返し、平氏拠点の六波羅に入ります。そして真っ先に二条天皇の身柄を確保し、そこに仁和寺を出た後白河上皇が合流します。
藤原信頼はこの非常事態の時に、清盛と縁戚関係にあったことで油断していたのです。藤原信頼は二条天皇という御旗を失い賊軍になり、逆に平清盛は後白河上皇と二条天皇から藤原信頼を討つ命を引き出したのです。
源義朝は逆賊扱いの身になったことで、京の源氏一門の協力を得られず、さらに東国源氏の足利義康はすでに病で亡くなっていました。
そのため義朝の味方は、義朝と共に京に上っていたわずかな東国武士のみでした。それでも一時は平氏軍を押し返し、六波羅に攻め寄る場面がありました。
しかし当主平清盛が出陣すると状況は一変したのです。清盛との戦いに敗れ、義朝は拠点の東国で再起を図るため、大原を抜けて近江に脱出します。
義朝は残った家臣(上総氏・三浦氏等)たちと分かれ、小勢バラバラに東国を目指します。しかし逃亡の最中義朝は、知多(今の愛知県)で襲撃され自害します。
そして京に残り後白河上皇に命乞いした藤原信頼は、許されず謀反の張本人として処刑されたのです。

反乱に加わっていた義朝の嫡男 源頼朝(みなもとのよりとも)は、逃亡中に父とはぐれて平氏に捕らえられます。
直接反乱に加わった者は通常処刑されるところですが、平清盛の継母 池禅尼(いけのぜんに)の助命嘆願があり一命を取り止めます。
助命嘆願の理由は諸説ありますが、頼朝が蔵人(皇族に仕える役人)として仕えた皇族の上西門院、また頼朝の母の実家 熱田大神宮家(藤原氏)等が助命を願ったと考えられています。
伊豆に流罪とされた頼朝は14歳で、平氏家人の伊東氏に監視されながら、乳母の比企局(ひきのつぼね)に世話をしてもらう生活を送ることになります。
また、幼く反乱に加わらなかった頼朝の弟 範頼(のりより)と牛若丸(うしわかまる)は、将来の出家を条件に藤原氏に保護されます。
東国武士の棟梁 義朝亡き後、東国では領地争いが起こります。義朝の領地の一部は常陸佐竹氏(義朝の叔父)に奪われ、また平清盛に味方した大庭氏が、上総氏や三浦氏に代わり権勢を奮うようになります。
東国は義朝の死によって情勢が大きく変わり、源氏の力が衰え平氏(平清盛)の支配力が強くなっていったのです。
平氏の時代の到来
1160年 都の争いが収まると、後白河上皇によって比叡山延暦寺と紀伊熊野神社から、京に新日吉神社と新熊野神社が勧請(仏の分霊を迎えること)されます。
この両社は院政が始まって以来上皇が訪れる寺社で、この勧請は後白河上皇の精神的拠り所を都に設けるため行われたのです。
新日吉神社
後白河法皇によって創建された由緒ある神社です。近江日吉山王の神を勧請したのが始まりで、社地は転々とし明治期に現在地へ。酒造、医薬、縁結びの神として信仰がある。
新熊野神社
平安後期熊野詣盛んな頃、後白河上皇が熊野の神をここに勧請するため創建された。境内の大樟は当時熊野より移植した後白河上皇お手植といわれています。
1164年 源氏の失脚により京の武家貴族は平氏中心になります。また朝廷では二条政権が誕生せず、平清盛と結託した後白河政権の院政があらためてスタートしていました。
信西と藤原信頼を失った後白河上皇は、新たな協力者に平清盛に目を付けたのです。
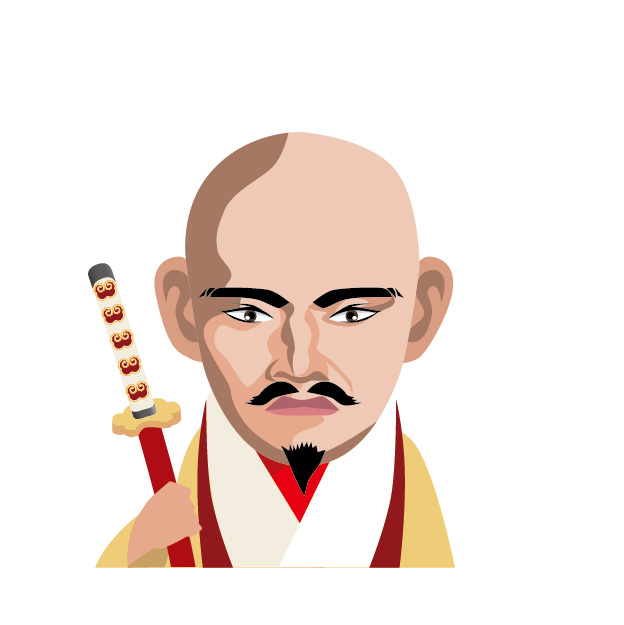


平清盛 後白河上皇
この年、平清盛は藤原氏(摂関家)と縁戚になり、後白河政権は後白河上皇・二条天皇・関白(藤原氏)・平清盛によって運営されることになります。
平清盛は後白河上皇との密接な関係を築くため、御所内に御堂 蓮華王院三十三間堂を建立します。この御堂は末法思想(釈迦の死後に訪れるとされた世の末期のこと)の世で、後白河法皇が極楽浄土を願うために造られたのです。
御堂の内部には千一体の観音像が配置され、かかった多額の費用は平清盛の資産で賄われ、これだけの御堂を個人が建立したことは、平氏の時代の到来を世に示すことになったのです。
蓮華王院 三十三間堂
三十三間堂は京都の国宝で、正式名称は蓮華王院(れんげおういん)です。
このお堂内は柱と柱の間が〝33〟もあり、南北120mもの長大な長さを誇る横の長さ日本一の木造建築です。建物に33の柱の間があることから通称を〝三十三間堂〟と呼ばれるようになりました。
三十三間堂は工夫を凝らし、天井の梁を二重にし地震の揺れを予測した組み方をすることで、揺れ動くようにして動力を逃がす免振工法がとられました。平清盛は建築技術に関して非常に先進的な考えを持っていたようです。
内部にはそれぞれ500体ずつの観音立像が並んでおり、50体×10列で左右均等に配置されています。圧巻の光景はさながら仏像の森の様でこれは三十三間堂にしかない特徴となっています。極楽往生を願う後白河法皇の強い願いが感じられます。
長い本堂を使用した〝通し矢〟という催しが桃山時代から行われ、軒下の廊下の南端から北端の的まで120mの距離を矢で射通していたといいます。現代でも1月15日に晴れ着姿の新成人による大的大会がおこなれており、京都の風物詩となっています。
1165年 二条天皇は皇子(六条天皇)に譲位した後、病で崩御されます。ついに二条政権が実現することはありませんでした。
二条上皇が崩御され、その機に清盛は平氏一門の血を引く皇子(高倉天皇)を皇位につける画策を行います。この皇子は公家平氏 平時忠(たいらのときただ)の妹、建春門院と後白河上皇の間に誕生していたのです。
さらにその翌年、関白 藤原基実(もとざね)が亡くなり、基実の妻 盛子(清盛の娘)が幼年の嫡男の後見人として資産を管理するようになり、実質的に平氏一門が藤原氏(摂関家)の巨大な経済基盤を支配することになったのです。
さらに平清盛はこれまでの軍功と寄進による功績で、武家貴族としては初の内大臣を経て太政大臣(朝廷の名誉職)に任命されます。これで清盛は武士としてではなく、公卿として朝廷内に見事に融和したのです。
1168年 六条天皇が譲位され、平清盛が推す皇子(高倉天皇)が即位されます。
平氏一門の力がますます増大する一方、清盛は平氏だけが都の責任を担うのはリスクが高いと考え、そのリスク分散に摂津源氏の源頼政(よりまさ)を引き立て、責任の一部を担わせるようにします。(平氏と源氏のパワーバランスを調整した。)
さらに源頼政は伊豆国主に任命されます。しかし偶然にも伊豆は源頼朝の流刑地であり、これ以降頼朝は、源頼政の力で守られることになります。
以後源頼政は、歌人として貴族間に人脈を広げ、武家貴族として王朝を守る源氏一門の長として存在感を示していくようになります。
都の上級貴族藤原氏の苗字
この時代では貴族たちにある変化が起こります。古来より天皇から賜る特別な性があり、それが藤原氏・平氏・源氏・橘氏です。
しかし平安時代後期になると、その性にあやかる強引な婚姻、また性を勝手に自称する者が現れ、藤原や平の性が増えすぎたことが問題になっていました。
そこで藤原氏等の貴族たちは、自身が住む地名を苗字とし、自身が所有する領地(財産)を主張すると共に、家格を明確にするようになります。
例えば最高貴族の藤原氏(摂関家)では、京の近衛大路、鷹司室町、京都九条、二条富小路、一条室町を苗字にし、藤原五摂家(関白・摂政を世襲する家)近衛・鷹司・九条・二条・一条としています。
平清盛による貨幣文化の発展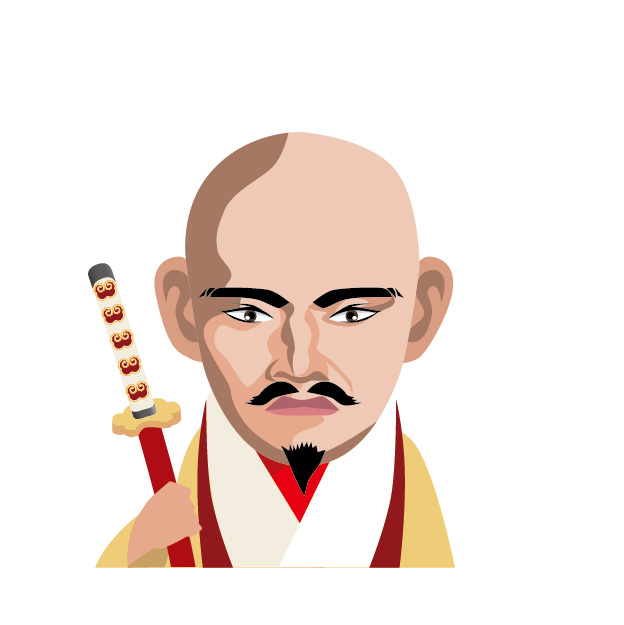
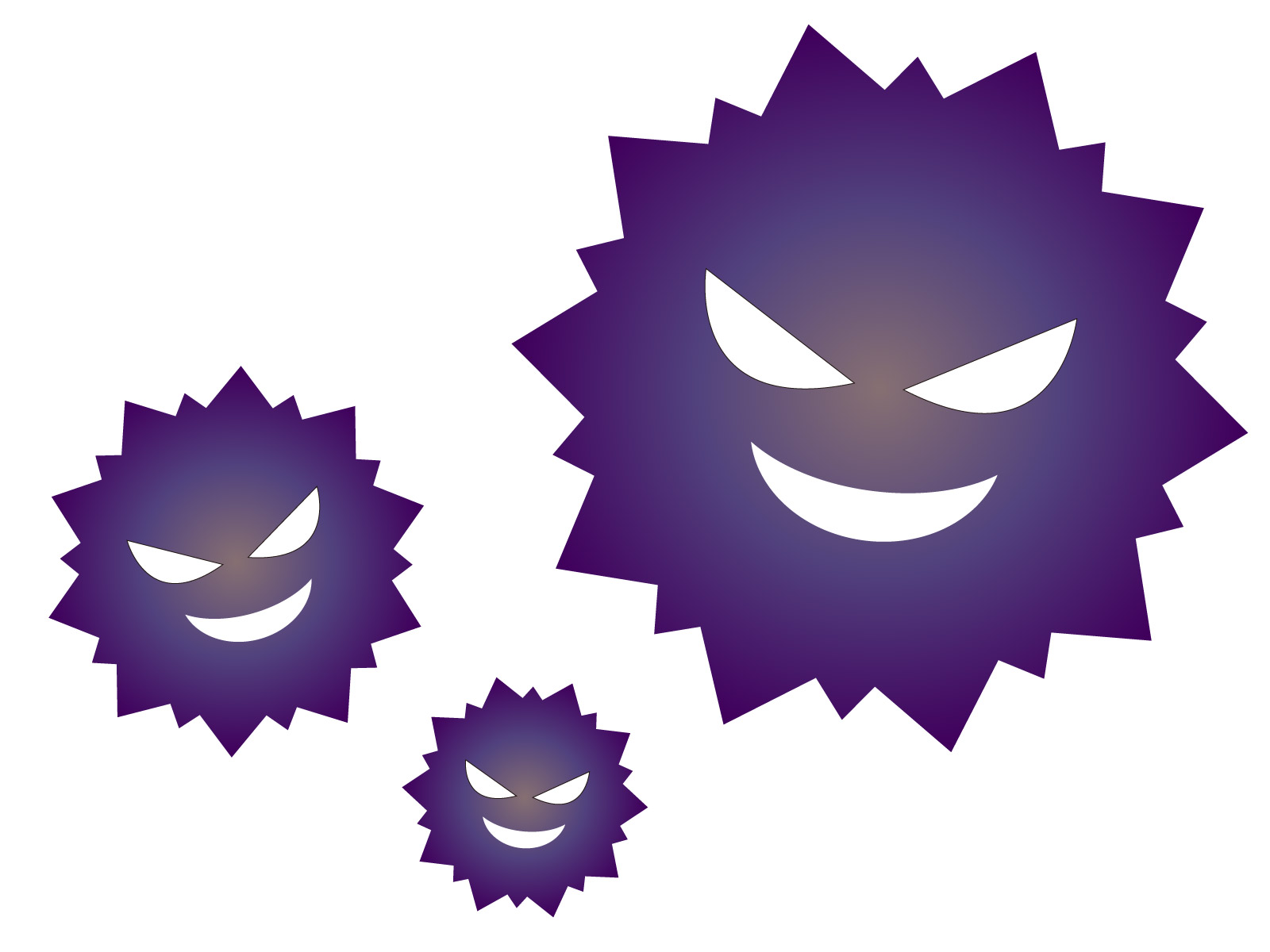
1168年 熱病にかかり重病になった平清盛は、回復した後出家します。これ以降名誉職の太政大臣を辞任し、都を息子たちに任せて半ば隠居し、瀬戸内海に面した福原(現在の神戸)を拠点にするようになります。
清盛はこの地で中国(宋)との貿易を発展させ、経済力を増強させます。この貿易で輸出された砂金は、東北の奥州平泉で産出されたものが使用され、後にマルコポーロの東方見聞録で、日本が黄金の国と伝えられる元になりました。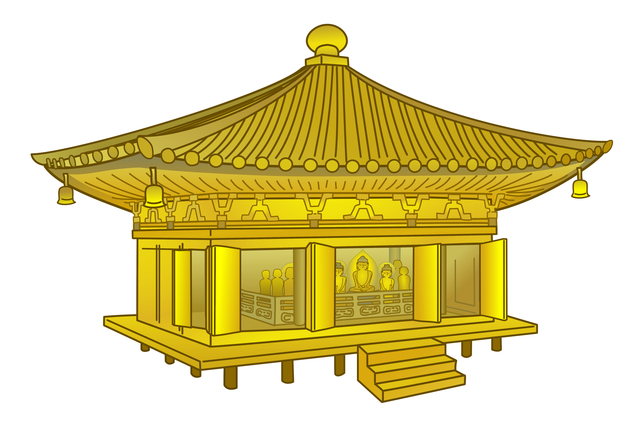
中国(宋)では宋銭(貨幣)が使用されていたため、日本でも貨幣取引が行われるようになります。この時代に日本で貨幣文化が発展したのです。
貨幣取引は中国(宋)の商人が使用するのを見て、博多商人たちがそれに習ったとされ、従来の絹取引に比べとても便利だったのです。清盛は宋銭(貨幣)を輸入することで、京の貴族が持つ絹の価値を下げ、その経済力を低下させたといいます。
また、安芸守(山陽道の行政区長)をつとめた経験を持つ清盛は、瀬戸内海の守護神 厳島神社を強く信奉していました。出家後清盛は、厳島神社を寝殿造に改修し平氏の氏神としてさらに篤く信仰するようになります。
厳島神社

厳島神社は創建593年、1168年に寝殿造り様式(平安時代貴族の邸宅建築様式)として現在の規模に造営されました。

海上に建ち並ぶ建造物群と背後の自然とが一体となった景観は、人類の創造的才能を表す傑作であること、建造物の多くは13世紀に火災に見舞われたが、創建時の様式に忠実に再建され、平安時代、鎌倉時代の建築様式を今に伝えていることにより世界文化遺産に認定されています。
厳島神社は奇抜な設計をしています。鳥居は海の中、社殿が海上に造られています。これは宮島が聖なる島とされていたためとされています。社殿は壮大で、浄土信仰に基づく極楽浄土をを表したものとされています。

厳島神社は基礎の石の上に柱をのせているだけで、満潮の際にはプカプカと浮く設計となっています。床板には隙間があり、波を逃がすことで波のエネルギーを弱めます。こうした工法により、厳島神社のご神体は高潮などでも水没しなかったとされています。
平氏と寺社勢力の争い
平清盛は少し前の1164年に、厳島神社に平家の繁栄を祈願して「平家納経」を奉納していました。これは当代の絵画・書跡・工芸の最高技術を駆使して華麗な装飾を施し、『法華経』、『阿弥陀経』、『般若心経』等からなる経典です。(現在国宝とされています。)
1174年 平清盛は後白河法皇と建春門院に同行して厳島神社詣に赴きます。これは厳島神社を氏寺とする平氏への、後白河法皇の配慮があったのでしょう。
後白河法皇は厳島神社の独特な建設様式と、回廊の下の波、また景観や巫女の舞を楽しみ、お手植えの松を残されたとされます。
しかし上皇がこのように遠方の寺社まで赴くことは異例で、また時の権力者である平清盛が、都の寺社(延暦寺や興福寺等)を差し置き厳島神社を強く信奉したことに、寺社勢力はよく思いませんでした。これが平氏一門と都の寺社勢力の関係が悪化するきっかけとなるのです。
さらに平氏一門は、藤原氏(摂関家)の家領(財産)を支配していたため、藤原氏氏寺の興福寺とは特に深い対立に発展していくのです。
平氏全盛時代の到来、そして衰退の始まり
1174年 平氏一門の力は絶頂期を迎えます。この年の正月に公家平氏の平時忠(たいらのときただ)が、〝此一門にあらざらむ人は皆人非人なるべし〟(平家にあらずんば人にあらず)と発言したとされます。これは平氏でない者は出世できないという意味です。
しかしそれからわずか2年後、後白河法皇の妃の建春門院(清盛の妻の妹)が35歳の若さで亡くなります。
建春門院は平氏と後白河法皇を結びつけるキーマンで、少し前に平清盛の娘徳子が高倉天皇の后となった際に、影で建春門院のはたらきがあったとされています。
その建春門院が亡くなると、後白河法皇と平清盛の関係は疎遠になり始めます。そして両者に疑心が生じたのです。
その翌年、清盛の専横に対して貴族たちが反発し、清盛打倒計画(鹿ケ谷事件)が勃発します。
貴族たちは平氏と寺社勢力(僧兵を持つ延暦寺等)を争わせ、その隙に反平氏勢力を結集し、平氏の弱体化を謀ったのです。しかしこの計画は畿内の武家貴族(源氏)から協力を得られず、密告によって発覚します。
この事件発覚からすぐに後白河法皇の近臣が捕らえられ、処刑または流刑とされました。
1179年 鹿ケ谷事件の後、平清盛の嫡男平重盛(しげもり)が失脚します。
平重盛は後白河法皇と親しく、平氏一門の中で貴族たちの評判が高い人物でした。しかし近すぎる距離感から、鹿ケ谷事件関与の疑惑をもたれたのです。
失意の中で平重盛(しげもり)は病によって亡くなります。重盛は貴族と平氏の関係を結びつける重要な存在であったため、その死が平氏衰退に繋がっていくのです。
鹿ケ谷事件以降、後白河法皇は増大する平氏の力を削ぐため、平氏一門の領地没収を計ります。

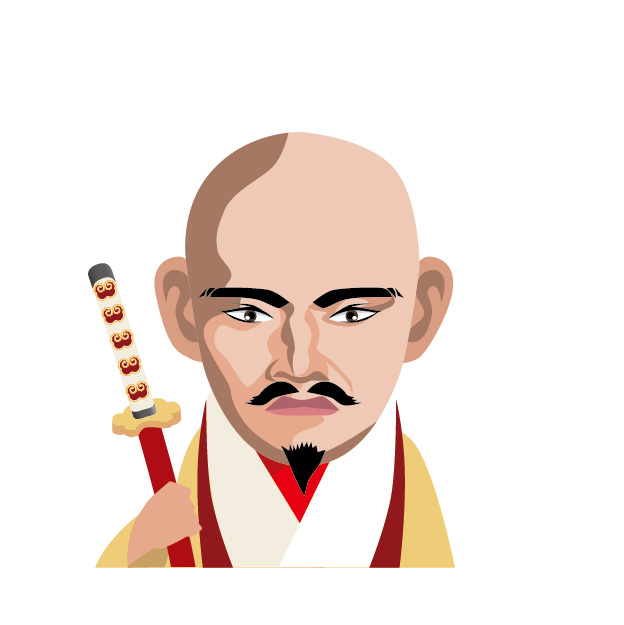
後白河法皇 平清盛
中でも平氏が実質支配していた藤原氏摂関家領を没収したことは、実質的な平氏一門への経済制裁と言えます。これ以降後白河法皇と平氏一門は真っ向から対立していくのです。
次の話
10分で読める観光と歴史の繋がり 源平合戦 有能な戦略家 〝源頼朝〟と〝最強の戦術家 源義経〟兄弟の争いと、裏で暗躍する後白河法皇/ ゆかりの京都 鞍馬寺、六波羅密寺、炎上する奈良 東大寺と興福寺
興味のある方はこちらもどうぞ!
中部観光ホームページ 歴史と共に巡る旅(石清水八幡宮・三十三間堂・六波羅密寺・鞍馬寺・貴船神社・宇治平等院鳳凰堂)
http://chubu-kanko.jp/平安時代-源氏と平氏の長く続く戦いのドラマを巡/


コメント