テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。
歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。
※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています!(諸説ありでよろしくお願いいたします。)
頼朝と義経の対立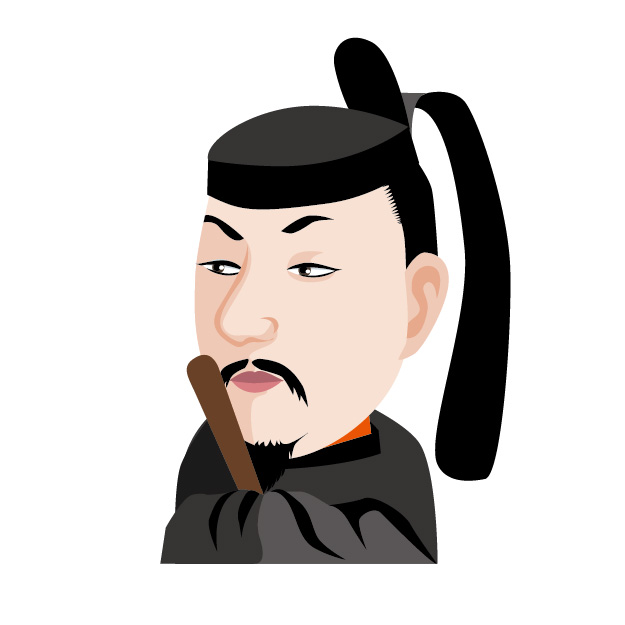

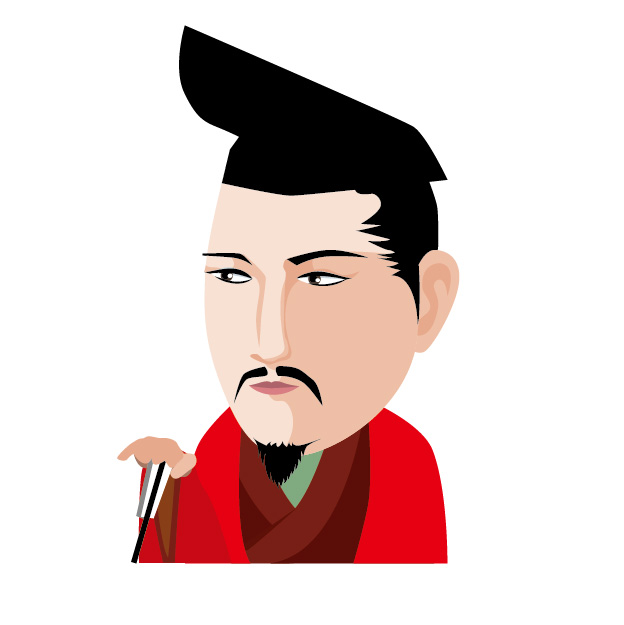
源頼朝 源義経
1185年 長く続いた源平合戦が終結しました。
この戦いで源頼朝は朝廷の大義名分を得た上で、木曽義仲や平氏一門等を朝敵に認定して倒し、没収した領地を中立武士に与えることで自勢力に取り込み、勢力を増大させていきました。
また頼朝は東国の常陸佐竹氏・下総氏・甲斐源氏等を粛清して弱体化させ、その類まれな戦略能力で武家の棟梁の地位を盤石なものとしたのです。
その一方で頼朝の弟、源義経は兄に代わり最前線で戦い、拙速を持って相手の虚をつく奇襲作戦、緻密な情報収集、さらに四国豪族や熊野水軍を調略して味方につけるなど、高い戦術能力を発揮して大功をあげました。
源平合戦集結後、頼朝は出世して公卿になり、義経は後白河法皇の親衛隊長に任じられます。
ところが戦を終えて意気揚々と凱旋する義経を待ち受けていたのは、東国豪族梶原景時からの独断専行に対する批判でした。
実際のところ義経は屋島や壇ノ浦の合戦等で、東国武士団と合流せず攻撃を仕掛けるなど、その独断専行に不満が出ていたのです。
梶原景時曰く、義経は〝平氏を包囲降伏させ、安徳天皇と三種の神器を京へ戻せ〟という頼朝の命令を無視し、その命令に失敗したというのです。
思いもよらぬ批判を受けた義経は、鎌倉に帰還せずに京に戻ったのです。
一方、京においては義経への後白河法皇の評価が高く、世間では義経こそ頼朝の後継者にふさわしいという声が聞こえていました。
このことが頼朝と義経の関係をこじらせたのです。頼朝には嫡男頼家(よりいえ)がいたため、後継者争いに発展することが危惧されたのです。
そこで頼朝は義経に鎌倉に戻るよう命じます。この時の頼朝はまだ事を穏便に済ませ、義経を自身の管理下で統制しようと考えていました。
しかし義経の脳裏には、過去に頼朝が行った上総氏や甲斐源氏等の粛清がよぎりました。
義経は後白河法皇を後ろ盾に、公家平氏平時忠の娘を妻にするなど、京で独自の居場所を築き、鎌倉帰還を拒否したのです。
しかしこの問題は収まらずに大きくなります。
頼朝は鎌倉に父(義朝)の菩提寺を建立し大掛かりな供養を行います。その供養に参列するよう義経に求めます。しかし義経が拒否したことで兄弟の関係は決定的に決裂したのです。
義経の決起と最期

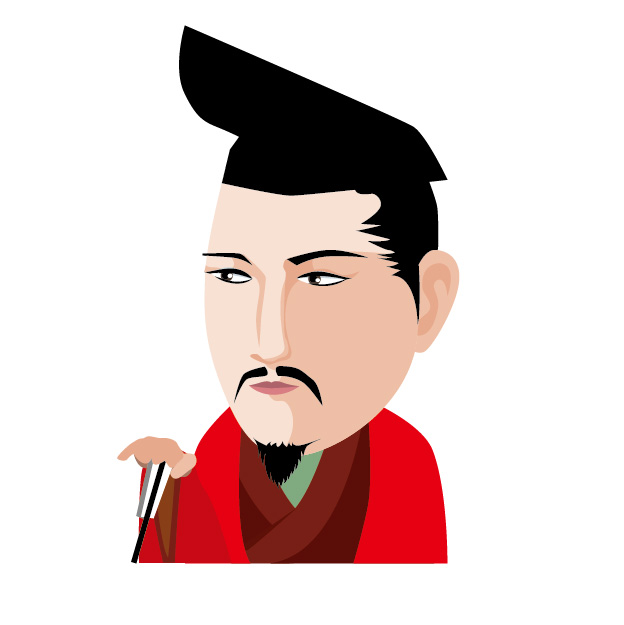
後白河法皇 源義経
義経は後白河法皇の下で美濃源氏・摂津源氏等と連携し、反頼朝勢力を結成します。さらにこの動きに源頼朝に反し、政権から疎外されていた豪族たちが加わります。
そうして後白河法皇から頼朝討伐の命を取り付けて決起したのです。
しかし源頼朝はこの危機にあせらず、自身に正統性がある事を源氏家人たちに伝えます。その一方で父(義朝)の供養に参列せず、不義で人望を無くした義経に協力する武士は少なかったのです。
予想外に兵が集まらなかった義経は、一旦決起を諦めて西国に落ち延びることにします。
北条時政
頼朝は京の地理に詳しい北条時政を派遣し、京都守護の任を与えて義経追討を命じ、時政は自身の政敵である義経を徹底的に追い詰めるのです。
その一方で頼朝は、西国に国地頭という強い権限をもつ軍政官を設置することを朝廷に認めさせます。
これは表向きは平氏残党や義経の反乱を防ぐための処置ですが、実のところ西国の荘園(私有地)を実質支配する目的がありました。
一路九州を目指す義経一行は嵐で渡航に失敗し、最後の頼りの綱である奥州平泉に向け陸上での逃避行を行います。
そして義経に与した摂津源氏や美濃源氏等、また共に戦った西国豪族たちは北条時政の追討軍に粛清されます。
1187年 源義経は北陸(安宅)を抜け、やっとのことでたどり着いた平泉で、奥州藤原氏の保護下に入ります。この時奥州藤原氏は源頼朝との対決が避けられないと考えます。
源頼朝は義経を匿う奥州藤原氏に、大仏再建を理由に膨大な砂金を要求し圧力をかけます。そんな折、奥州藤原氏の当主 秀衡(ひでひら)が亡くなります。藤原秀衡は遺言で義経を大将軍にして頼朝に対抗するよう命じるのです。
一方頼朝は朝廷から義経追討命を引き出し、奥州藤原氏にさらなる圧力をかけます。ここで頼朝はあまり敵を追い詰めると結束すると考え、じわじわと時間をかけて奥州藤原氏と義経を分断する離間の計を開始します。
1189年 奥州藤原氏はとうとう圧力に耐えかね、義経を襲撃して義経は自刃します。
義経は平氏との戦いでは見事な戦術で勝利を収めましたが、頼朝との争いでは戦わずに敗れ、悲劇の英雄の死を遂げたのです。
奥州合戦勃発
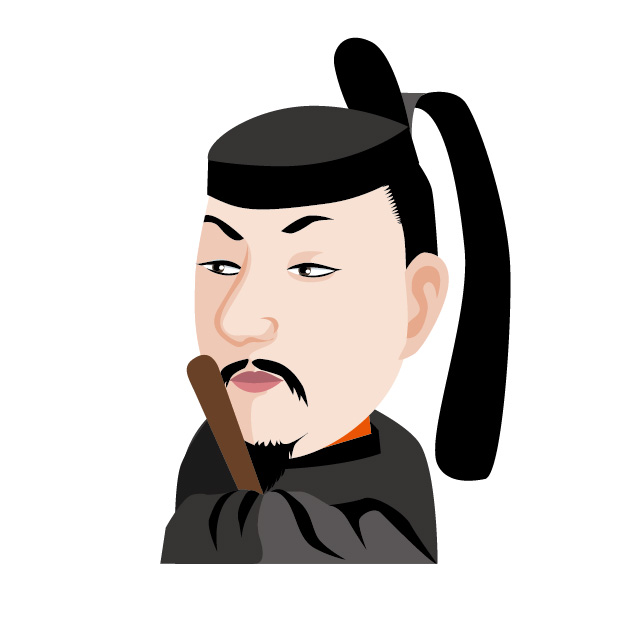
朝廷は義経の死で争いが集結したと考え、奥州藤原氏追討は考えていませんでした。しかし源頼朝は、大勢力奥州藤原氏の存在を認めたくありませんでした。
唯一の官軍を自称する頼朝にとって、奥州藤原氏は強大な敵対勢力で、どうあっても容認できなかったのです。
1189年 奥州合戦が勃発、これが源頼朝の最終戦争となります。この戦には日本全国から武士が集められ、西は九州の薩摩、さらに敵対していた常陸佐竹氏も含め、総勢17万の大軍団が結成されます。(この時に頼朝は、後白河法皇を後ろ盾とし旧平氏家人を自らの勢力下に統一しています。)
遠征軍は頼朝と畠山氏が下野国(栃木県)から入り、千葉氏等は常陸国(茨城県)から、比企氏等が越後からと、三方向から一気に攻め込む大規模軍事行動を開始します。
奥州藤原氏と阿武隈川付近で戦になり、畠山重忠を中心に波状攻撃を仕掛けて撃退します。さらに三浦氏・和田氏等が阿津賀志山防塁を攻めて陥落させます。それを知った奥州藤原氏は逃亡し、頼朝軍はその行方の捜索に入ったのです。
頼朝軍は捜索を続けながら平泉へ入ると、すでに奥州藤原氏の手で平泉の館には火が掛けられ、平泉の都は灰になっていたのです。しかし幸いなことに、中尊寺・毛越寺・大長寿院などの寺社の多くが無傷ですみました。
平泉制圧後奥州藤原氏当主は殺害され、頼朝は背後の憂いをなくし、ついに念願の上洛を果たすことができるようになったのです。
源頼朝の上洛

1190年 上洛を果たした源頼朝の武者行列は、その規模の大きさで貴族たちの度肝を抜いたとされます。
そこで頼朝は後白河法皇とおよそ30年ぶりの対面を果たすことになります。
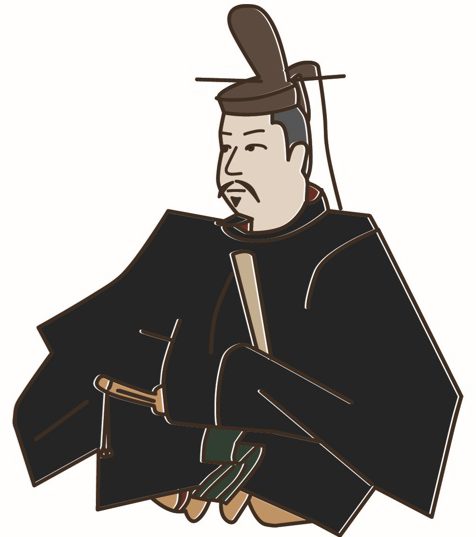
後白河法皇 源頼朝
源頼朝は後白河法皇と会談した後後鳥羽天皇に拝謁し、頼朝は王権を支える官軍であることを世間に示します。
また頼朝は公卿の九条氏と面談し摂政として支援する協力体制を構築します。またこの時に戦時下の新恩給与(戦で奪った地を家人に与える)に変わる、新たな制度について話し合ったとされます。
その後、頼朝は公卿に任じられ、さらに10人の家人(和田氏・三浦氏・比企氏・梶原氏・千葉氏、他)にも官職が授けられて鎌倉に帰還します。
1192年 後白河法皇が崩御されます。源氏と平氏の間に翻弄されながらも、最後に王権を確立した波乱万丈の生涯を遂げられたのです。
その同年に頼朝は朝廷から大将軍に任じられます。朝廷は〝征東〟や〝惣官〟は、平氏や木曽氏が使用したので不吉とし、かつての英雄 坂上田村麻呂にならい〝征夷〟が選ばれたとされます。
これ以降は将軍直属として仕える武士を御家人と呼ぶようになります。
御家人には地頭職(主に管理・徴税の任)や、守護職(主に軍事警察の任)が与えられ、守護職を務める御家人に三つの権限(大犯三箇条)が与えられます。
その権限の二つは、謀反と殺人に対する検察権と断罪権です。そして三つ目が大番役(京や鎌倉における警護役)を任じる権利です。頼朝は名誉な大番役の権利を御家人に限定したのです。
頼朝は御家人を統制するにあたり朝廷の官位を活用するようにします。(官位は全国共通の肩書として武士社会で権威を発揮していました。)
これまでの武士は官位を得るため、貴族との人脈に頼っていました。しかし頼朝は幕府の推挙がなければ朝廷の官位を受けてはならないと定めます。
この官位推挙権を、新恩給与に変わる報奨制度としたのです。
これらのことから名実ともに幕府体制が成立し、軍事警察権を鎌倉幕府が独占することで、内乱の時代が終息したのです。
院政から武家政治への移行
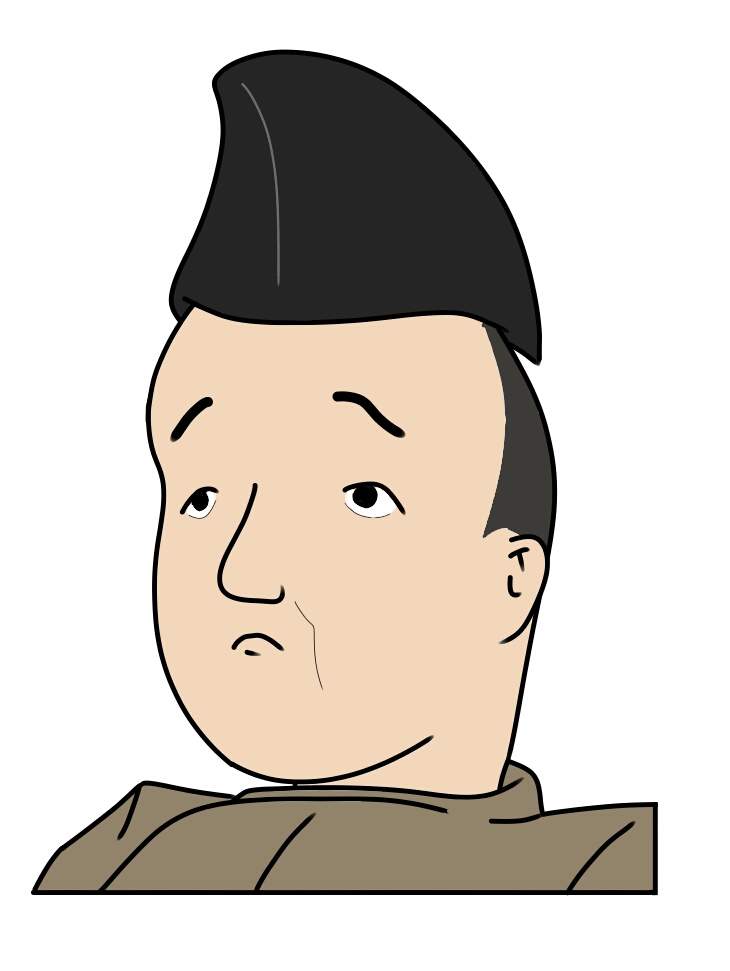
後白河法皇の死後、孫の後鳥羽天皇は13歳だったため、源頼朝と関白九条氏が政治を担うことになります。
鎌倉幕府成立後、政治の中心機能の一部は鎌倉に移り、それに伴って重要祭事の多くが鎌倉の鶴岡八幡宮で行われるようになります。
鶴岡八幡宮
源氏の先祖源頼義が京から分霊を移して始まった八幡宮は、1180年頼朝挙兵時に現在の位置に移され、以後放生会(殺生を戒める宗教儀式)や流鏑馬(馬に乗って矢を射、魔を払う天下泰平のための神事)、相撲、舞楽などが行われるようになる東国の社会的中心の場となりました。
特に流鏑馬は盛んにおこなわれ、鶴岡八幡宮に奉納するために作られた国宝・黒漆矢は破魔矢の起源とされています。(鎌倉国宝館に収蔵)

頼朝の晩年
1192年 北条政子は頼朝の子、千幡(実朝)を授かります。頼朝は晩年に授かった千幡(実朝)に深い愛情を注ぐようになります。
千幡(実朝)の乳母は北条氏が努め、祖父北条時政が盛大に祝賀を行います。二人目の男児千幡(実朝)は、頼朝の後継者のバックアップとなり鎌倉幕府は安定したのです。
一方頼朝の後継者の本命は、やはり嫡男 頼家(よりいえ)です。
頼朝は頼家が誕生した際には安産を願い、かつて由比若宮(源氏の氏神を祀る社)があった由比ケ浜から、鶴岡八幡宮に至る路の整備を命じるほどの力の入れようでした。なお鎌倉はこの時に完成した若宮大路を中心に都市整備されます。
若宮大路

1193年 ここまで順調だった鎌倉幕府に不穏な事件が起こります。
頼朝が征夷大将軍として権威を示す鹿狩りが行われ、嫡男頼家は初の鹿狩りを見事に成功させます。ところがこの晴れやかな場で、仇討ちと称する惨殺事件が起こり、多くの御家人が巻き込まれたのです。

この事件は頼朝にまで危険が迫り、事件関係者への粛清の嵐が吹き荒れます。そして頼朝は弟の源範頼が事件に関与していたと断定し、謀反の罪で処刑します。さらに源氏一門の安田氏(甲斐源氏)も、謀反の嫌疑で処刑されています。
諸説ありますが戦時から平時に移行する過程で、御家人同士の不満・反発によるクーデターが起こったと考えられます。結果的にこの粛清で後継者の頼家の地位は盤石になったのです。
1195年 源頼朝は源平合戦で焼失し、再建された東大寺大仏殿の完成を祝うために二度目の上洛を行います。ここで朝廷に後継者 頼家のお披露目がなされました。
晩年頼朝は娘を内裏(天皇の住まい)に入れ、天皇家の親族となり朝幕の関係を安定させようと試みます。しかし直前に頼朝の娘が亡くなり計画は頓挫します。
これにめげず頼朝は後継者頼家の正妻に、源氏一門で家格が高い美濃源氏(賀茂氏)の娘を選び、鎌倉幕府の安定を図ります。
また、旧平氏勢力が残る九州統治のため、側近の大友氏を守護に任命し、御家人の島津氏や少弐氏と共に九州のまとめ役とします。このように頼朝は人生の総仕上げとして鎌倉幕府を安定させるために動いたのです。
1199年 源頼朝は病で亡くなります。頼朝はこの年に上洛を計画していたため、急死であったと考えられます。
この緊急事態に、鎌倉幕府は有力御家人13人が集まり吉書(天皇に奏上する文書)を作成します。
そして貴族出身の大江広元(おおえひろもと)が京の御所正殿で披覧(文章を開くこと)し、ニ代将軍 源頼家の後継が朝廷に認められ、幕府存続は無事公認されたのです。
この時の源頼家はまだ18歳で、戦の経験すらありませんでした。そこで有力御家人13人が合議制で補佐する新体制が始まるのです。
新仏教の誕生
鎌倉時は時代の変化と共に仏教が発展します。平安時代は国家を守る国家仏教として、天台宗(延暦寺)と真言宗(東寺)が存在しました。その主な役割は新たな寺社の建立と、国家と皇族や貴族のために神事を行う事でした。
しかし社会の転換期となった鎌倉時代は、武士と農民が存在感を高めます。彼らは長く続いた戦乱に不安を抱き救いを求めていたのです。
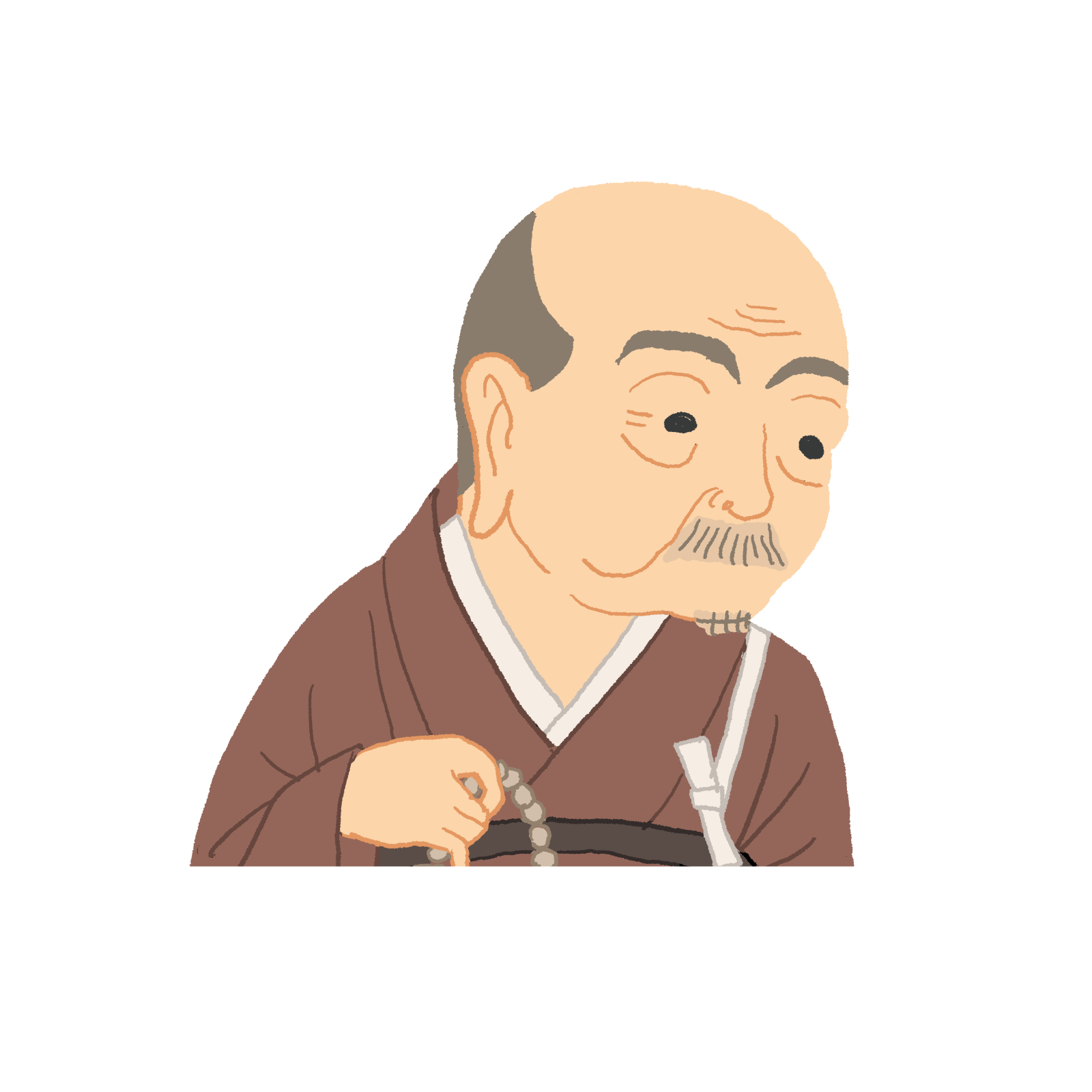
この願いに応えるようにして新仏教が生まれます。
浄土宗の開祖法然(ほうねん)は、比叡山延暦寺で修業して悟りに達します。法然は比叡山を降り、「厳しい戒律を守ったり、難解な教義を学ばなくても、日常生活と共に信仰を行い、南無阿弥陀仏(念仏)と唱えれば、皆が救われ極楽浄土にいける」と説いてまわりました。
しかしこの教えが旧来の寺社勢力から反発を受け、法然は讃岐に流刑とされます。しかし後に京への帰還が許され、最後は京の東山大谷で亡くなります。法然の死後も浄土宗の教えは民衆に広まり、そして浄土宗の寺院が建立されました。
浄土宗の拠点は京の東山にありました。この地には法然の廟が作られ、浄土宗総本山知恩院として知られています。
知恩院
知恩院は浄土宗の開祖、法然上人が入寂された遺跡に建つ京都の由緒ある寺院です。
京都・東山の華頂山のふもとに、大小数多くの伽藍がひろがる、浄土宗総本山知恩院の壮大な佇まいは、厳粛な中にもおおらかな雰囲気をたたえ、お念仏のみ教え発祥の地にふさわしく人々を迎え入れてきました。

山門は徳川将軍秀忠公の建立で、24mもの高さを持つ国宝です。法然上人の御影(みえい)を祀る「御影堂(みえいどう)」は徳川将軍家光公の建造による壮大な伽藍で国宝です。
また、知恩院には古くから伝わる七不思議があり、方丈庭園に七不思議を巡るルートがあります。

一方で武士を中心に広がりを見せたのは禅宗の臨済宗です。開祖の栄西(えいさい)は、比叡山延暦寺で天台密教を学びました。
栄西は二度(1168年、1187年)宋(中国)に渡り、そこで学んだ禅宗を日本に伝えようとします。しかし旧来の仏教が根付く京での布教を断念し、鎌倉に移り布教を開始します。
禅宗は座禅を組み、師から与えられる問いを考え抜き悟りに達します。特に今この時に集中する不動心の教えは武士の気質にあい、鎌倉武士を中心に広がりをみせます。
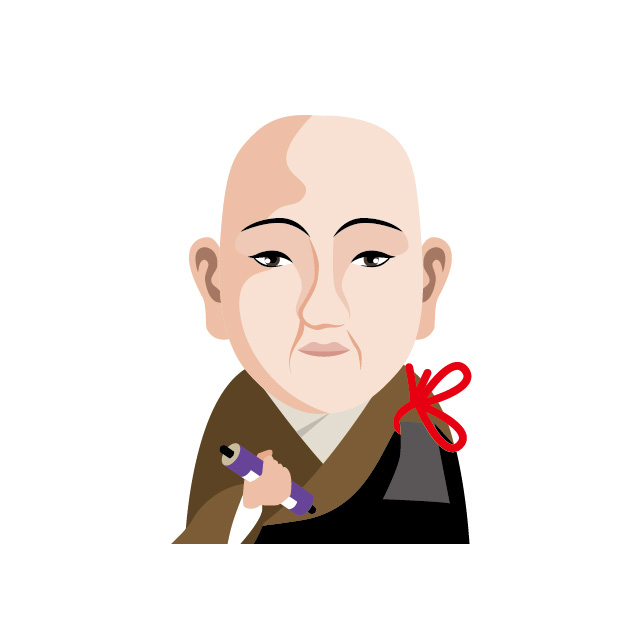
1200年 源頼朝の妻 北条政子(ほうじょうまさこ)は、頼朝の一周忌に栄西を招いて弔うための寿福寺を建立し、栄西はその住職となったのです。
寿福寺
神奈川県鎌倉市扇ヶ谷にある臨済宗建長寺派の寺院で、鎌倉五山第3位の寺院。この地は源氏の先祖源頼義が東北の乱、前九年の役に出陣する際、戦勝祈願を行った〝源氏山〟を背にした地で、頼朝の父・義朝の館があった場所でした。
門をくぐると鎌倉随一と言われる石畳の美しい参道がお目見えします。
頼朝の妻政子が建立した頼朝の菩提寺であり、敷地内に北条政子と三代将軍実朝の墓とされる五輪塔があります。
北条政子とニ代将軍頼家は栄西を精神面で頼りにしたとされます。そして将軍頼家は臨済宗を支援し京に大本山 建仁寺が建立します。
これ以降朝廷は国家仏教の天台宗・真言宗、鎌倉幕府は臨済宗が幕府の仏教として位置付けられます。
建仁寺
建仁寺は臨済宗建仁寺派の大本山で、建仁2年(1202年)に開創しました。開山は栄西禅師、開基は源頼家です。
当時の元号を寺号とし、室町幕府により中国の制度にならった京都五山が制定された際は、その第三位として厚い保護を受け大いに栄えます。
しかし戦乱と幕府の衰退により一時荒廃しますが、徳川幕府の保護のもと堂塔が再建修築されました。

建仁寺では禅寺体験として座禅や写経などの体験を行っています。また、国宝 風神雷神の屏風絵や、法堂の天井絵双龍図が有名です。
二代将軍頼家の政治
1199年 圧倒的なカリスマ源頼朝亡き後の二代将軍頼家の新体制が始まります。
鎌倉幕府は将軍頼家をトップに、頼朝の妻政子が家長、そして頼朝が任命していた侍所(軍事・警察担当)の梶原氏、政所(財政や政務担当)の大江氏、問注所(裁判や文書担当)の三善氏等を中心に運営されます。
そして御家人たちは将軍家の親族衆に伊豆 北条氏、武蔵 比企氏、また宿老として相模の三浦氏と和田氏、北関東の八田氏等が存在感を持っていました。
彼ら宿老による13人の合議制は、将軍頼家への訴訟取次とその命令の執行を職務としました。
将軍頼家は合議制を通して受けた訴訟、主に地頭(御家人)と地方領主(非御家人の貴族・武士)との争いを調停するため、公正な判決を下していたようです。
また将軍頼家は土地調査に対し熱心に取り組み、領地の再分配を行う等の合理的な政策を行い、また鹿狩りを積極的に行うことで将軍の武威を示したのです。
頼家は武芸の他に蹴鞠の才能がありこれは朝廷政治に必要な重要な技能です。なんにせよ頼家の幕政は13人の合議制により順調なスタートを切ったのです。
御家人同士内乱の時代
ところが安定して見えた13人の合議制は、宿老たちの間に地域(伊豆・相模・武蔵等)の派閥が存在していました。
その派閥争いで孤立したのが、かつての頼朝の腹心梶原景時(かじわらかげとき)です。
梶原景時はかつて宿老の和田氏から侍所別当の役を奪い、秘密警察として活動して源義経を讒言で失脚させ、その他にも多くの御家人から恨みを買っていました。
ある時梶原景時は、有力御家人の結城氏を讒言し陥れようとします。これに結城氏は宿老たちに助けを求め、宿老の和田氏を中心に梶原景時への糾弾が起こります。
政所の大江広元が将軍頼家に取次ぎ、そこで弁明できなかった梶原景時は失脚します。
後に再起を目指して独断で京に向かった梶原景時は、その途上で御家人の追討を受け、一族もろとも滅亡したのです。
将軍頼家が頼りにした忠臣景時の滅亡により、幕府内のパワーバランスは崩れ始めます。そして対立は親族衆の比企氏と北条氏に起こります。


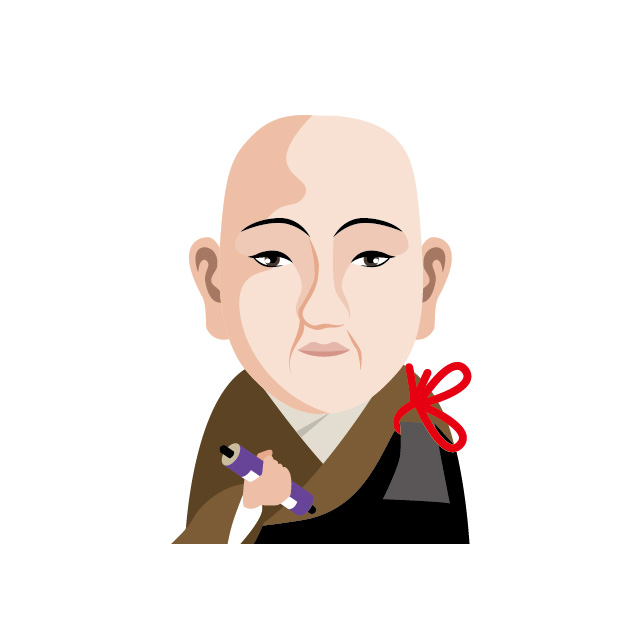
北条時政 北条政子
梶原景時亡き後、将軍頼家は乳母役の比企氏を頼りにし、比企氏は勢力を増大させました。その一方で北条時政は家長の北条政子の支援を受け、家格を上昇させて比企氏に対抗したのです。
将軍家親族衆の両家の対立は、将軍頼家が病にかかり危篤になったことをきっかけに決定的となります。
実のところ将軍頼家の乳母役を努める比企氏に対し、北条氏は頼家の弟千幡(実朝)の乳母役を務めて支持していました。
当然比企氏は頼家の嫡男一幡を後継者に支持します。つまり比企氏と北条氏の争いは、実質的な将軍家後継者争いになったのです。
その政争を制したのは北条氏でした。正当性でいえば嫡男一幡を擁する比企氏が優位でしたが、その油断をついた北条時政は比企氏と一幡を急襲して討ったのです。
この争いで北条時政が御家人たちの支持を得られたのは、そのバックにいる家長 北条政子と千幡(実朝)のおかげであったと考えられます。
ところが争いが集結した後、頼家が奇跡的に危篤状態から回復します。我が子の一幡が討たれたことを知った頼家は、北条時政を討とうと立ち上がりますが、母 北条政子に制止されます。
また、この時の頼家は臨終出家(死の前に極楽浄土を願い出家する)していたため、権力の座は千幡(実朝)と北条氏に移行し、御家人たちは頼家の命に従わなかったのです。
それから頼家は北条時政の命で伊豆に幽閉、政権安定を目的に暗殺され、23歳の若さで亡くなるのです。
北条時政の専横と失脚
二代将軍頼家と比企氏滅亡後、 三代将軍 源実朝(みなもとさねとも)の時代が始まります。
1203年 千幡(実朝)は後鳥羽上皇に将軍職継承が認められ、この時後鳥羽上皇から〝実朝〟の名を賜ります。
そして鎌倉幕府の政治は若い実朝を支えるため、御家人筆頭北条時政(ほうじょうときまさ)が主導するようになります。
1204年 北条時政は朝廷と幕府の関係を配慮し、後鳥羽上皇の親族坊門氏から、将軍実朝の妻を迎えます。
また北条時政は滅亡した比企氏の領地、武蔵国の掌握のため暗躍します。そうすると同じ武蔵国を領地とする畠山氏が邪魔になるのです。
そこで北条時政は、畠山重忠に謀反の嫌疑をかけ、嫡男の北条義時(ほうじょうよしとき)に命じて追討させます。
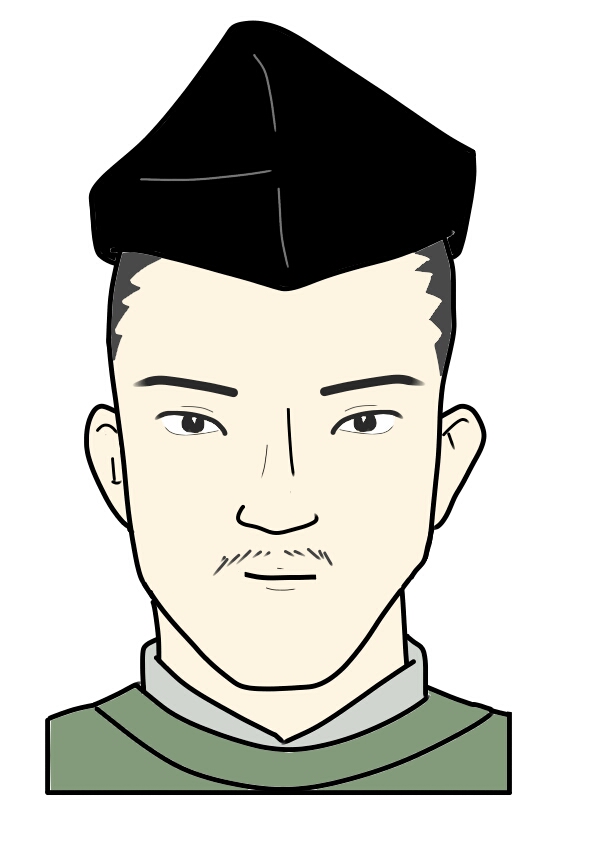


北条義時 北条時政
北条義時はあまりの兵の少なさに畠山氏の謀反は偽りと考え、義兄弟の関係にある畠山重忠の死を悼みます。これを機に義時は父 時政と対立するようになるのです。
また畠山重忠は源頼朝に重用され、大功を挙げた名高い武士だったため、疑惑のある北条時政に対する御家人の信用が失墜します。
北条時政の力に陰りが生じ、北条政子と義時への支持が高まります。そこで北条時政は起死回生の大博打に出たのです。
なんと将軍実朝に代え、自身の娘婿平賀氏(源氏一門で源頼朝の養子)を四代将軍にするべく画策します。
しかし窮地の将軍実朝を母北条政子が救うのです。北条政子に助けを求められた御家人三浦義村(みうらよしむら)は将軍実朝をすぐさま確保します。そして将軍を確保した北条義時と三浦義村は御家人たちを味方につけ、北条時政派に勝利します。
これで万事休した北条時政は出家して伊豆に隠居したのです。
新古今和歌集と後鳥羽上皇
1205年 新たに始まった北条義時による政治は将軍実朝の成長に伴い安定します。
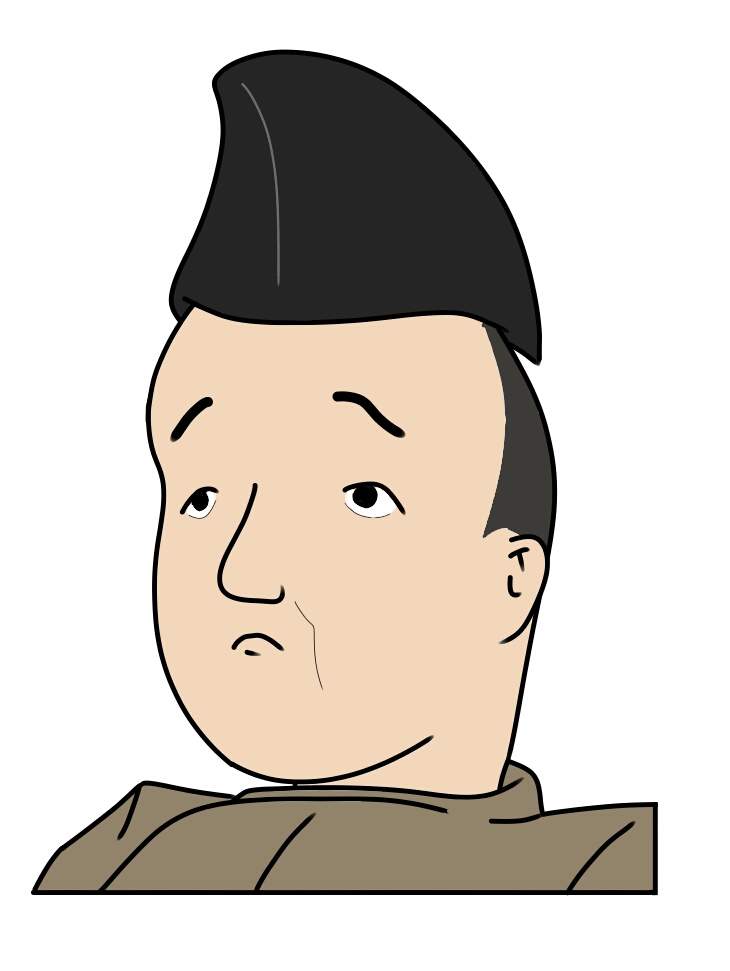
一方京の都では後鳥羽上皇が〝新古今和歌集〟編纂を命じ、華やかな和歌文化が広まっていました。
後鳥羽上皇は自ら選定した和歌を編集した新古今和歌集を、国家的な史書として完成を祝います。
後鳥羽上皇が詠まれた和歌には、〝奥山の おどろが下も 踏み分けて 道ある世ぞと 人に知らせん〟(たとえ奥山の藪の中に分け入ろうとも、必ず希望の道があることを人々に知らせたい)があります。
後鳥羽上皇は〝和歌は世を治め 民をやはらぐる道である〟と言い、新古今和歌集によって、民を和やかにする治世を行う王であると示したのです。
また後鳥羽上皇は長い戦乱で廃れた宮廷儀礼の復活を行い、国土安泰・五穀豊穣を実現しようと考え、平安時代の貴族日記から儀礼を学び貴族に教育を行います。
このように和歌、蹴鞠、琵琶の他、政治に優れた後鳥羽上皇は、英雄の資質がある人物と言えるでしょう。
このような京文化に魅入られた将軍実朝も和歌や蹴鞠をたしなみ、京の華やかな文化に適応していきました。実朝は後鳥羽上皇と蹴鞠で親睦を深めていくのです。
源実朝の政治
1209年 三代将軍実朝は、文化・帝王学・仏法を学び、為政者として成長し、朝廷の公卿(大臣)になります。
また宿老筆頭の北条義時と政所の大江広元等の補佐を受けて、将軍実朝が判断を下す将軍親裁を開始します。
将軍実朝は関東支配を固める政策を行い、社寺の経済基盤を安定させ、交通手段の要となる馬の安定供給を行い、都をつなぐ東海道の整備を実施します。
ところが地道ながら順調に将軍親裁を行う将軍実朝に試練が訪れます。きっかけは侍所別当の和田氏が将軍実朝に上総介(四位の貴族)の官職を求めたことにあります。
これは大豪族三浦氏の長老として、執権北条義時に対抗する目的があったと考えられます。結局のところ北条政子・義時等の反対や後鳥羽上皇の意向により実現しませんでしたが、これが遺恨となります。
それから数年が立ち、1213年 北条義時への反乱計画が勃発します。一部の豪族たちに二代将軍頼家と子一幡の殺害への反発があったと考えられます。
この反乱には和田氏も含まれていたため、和田氏と北条氏の争いにしたのです。将軍実朝の仲裁も功を奏さず、和田氏は決起したのです。
和田合戦は和田氏と三浦氏を中心に起こりましたが、三浦義村が北条氏側に寝返り、将軍実朝の確保に失敗します。
当然御家人たちは、将軍実朝と北条氏に味方し、足利氏、武田氏、その他豪族たちが和田氏を追い詰めて討ち果します。
この戦は将軍実朝の将軍権力が勝敗の決め手となったのです。
これ後北条義時は政治を司る政所と、軍事を司る侍所を兼ねた執権として、将軍に次ぐ地位を揺るぎないものにします。また、今回の件で義時に恩を売った三浦義村の存在感は、幕府内で大いに増大したのです。
源氏将軍家滅亡
和田合戦集結後、合戦の原因が朝廷への官位嘆願にあったことから、政所の大江広元が官位による御家人統制システムを統制します。(個人による官位嘆願の禁止等)
さらに将軍実朝は幕政の中心に、北条政子・北条義時・三浦義村・大江広元等を据えて幕府の安定を図ります。
このような動きは後鳥羽上皇から将軍実朝への信頼に繋がり、実朝は権大中納言・中将という高位に出世したのです。
しかし鎌倉幕府には大きな問題が一つありました。将軍実朝の後継者問題です。
実朝には正妻しかおらず、子供が一人も生まれていなかったのです。
そこで幕府首脳陣では、後継者を源氏一門(摂津源氏・足利氏・武田氏等)の中から検討していました。ところが将軍実朝はまったく別の考えを持っていたのです。
それは後鳥羽上皇の皇子を将軍とし、実朝が後見する親王将軍計画です。これは先祖源頼朝の血統を越える、皇族を将軍にするとても大胆な発想でした。
これに幕府首脳部も賛同し、さらに後鳥羽上皇も信頼する実朝と自身の皇子が幕府を運営しコントロールする、朝幕両者にとって良い案だったのです。
将軍実朝はこの計画を進めるに当たり、さらなる昇進を遂げ右大臣となり、本来武士では到達できない高い地位に上り詰め準備に入るのです。
ところがもう少しという時に、将軍実朝は突如暗殺されてしまうのです。
暗殺の首謀者は二代将軍頼家の遺児、公暁(くぎょう)です。この時公暁は鶴岡八幡宮の別当(寺務の総括者)を務めていました。
公暁は母 北条政子のはからいで僧として出世する道を与えられ、さらに政子が信頼する三浦義村が後見人になっていました。
1219年 将軍実朝の右大臣出世の祝いが鶴岡八幡宮で行われ、雪の降る石段を下る最中、実朝は襲いかかる公暁に殺害されます。
この時公暁は実朝のことを〝親の仇〟と呼びます。そしてその場から逃走した公暁は、後見人の三浦義村に〝私が将軍になる〟ことを伝えたのです。
しかしそれを聞いた三浦義村は、すぐさま北条義時に通報し、公暁は義時の命で討ち取られ、これにより源氏将軍家は断絶します。
この事件の真相ははっきりとしませんが、公暁はもし将軍実朝に子供が生まれなければ、自分が四代将軍になれると考えた。しかし親王将軍(皇族将軍)が実現してしまえばその可能性は永遠に無くなる。このあせりによる犯行と考えられます。
また、実朝を将軍(頼家)の仇にし、暗殺を正当化しようとしたとも考えられます。これによって後見人の三浦義村が後ろ盾になってくれると考えたのでしょう。
しかし公暁は実朝と同時に狙った執権北条義時の暗殺に失敗しました。これが公暁の命取りになったのです。
朝廷との対立
京では後鳥羽上皇が実朝殺害にショックをを受け、さらにこのような大失態を犯した幕府に強烈な不信感をもちます。とても自分の子(皇子)を将軍にすることなどできないと考えたのです。
また後鳥羽上皇はこの失態の責任が執権北条義時にあると考え、以降北条義時に敵意をもつようになるのです。そしてこれは後に承久の乱の一因となります。
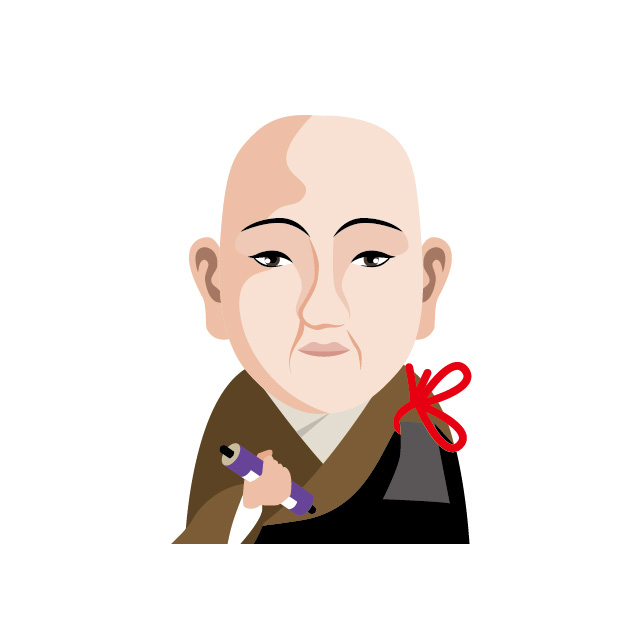
将軍後継問題は後鳥羽上皇との話し合いが決裂し、北条政子は三浦義村の提案を受け、源頼朝の姉の〝ひ孫〟にあたる、藤原氏(九条家)の三寅(みとら)を、未来の将軍として鎌倉に迎え入れます。
三寅はわずか二歳であったため、成長するまで北条政子が後見人となり、将軍権限を持つ、〝尼将軍〟になったのです。
次の話
10分で読める観光と歴史の繋がり 親子二代で日本の武士を一つにまとめた北条時頼と時宗、異国からの侵略者 元寇 これぞ武士の誉れ /ゆかりの古都鎌倉の寺院 高徳院(鎌倉大仏)、建長寺、明月院
興味のあるかたはこちらもどうぞ!
中部観光ホームページ 歴史と共に巡る旅(鎌倉大仏、鶴岡八幡宮、明月院、建長寺)

コメント