テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。
歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。
※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています!(諸説ありでよろしくお願いいたします。)
頼朝と義経の兄弟対立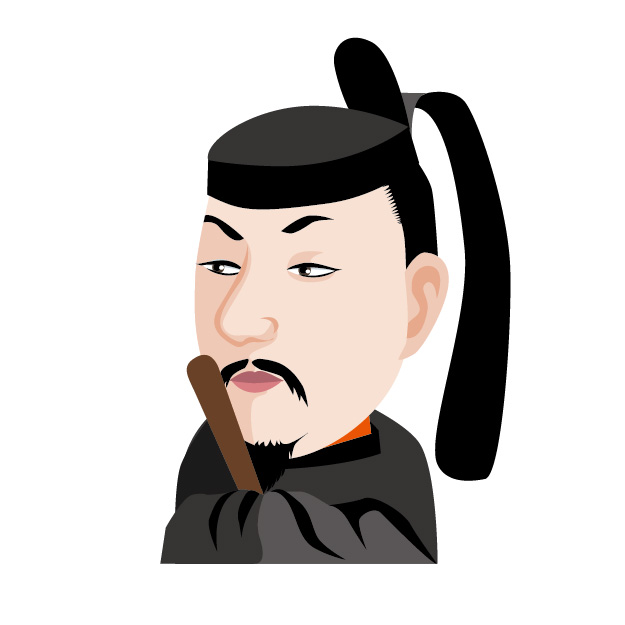

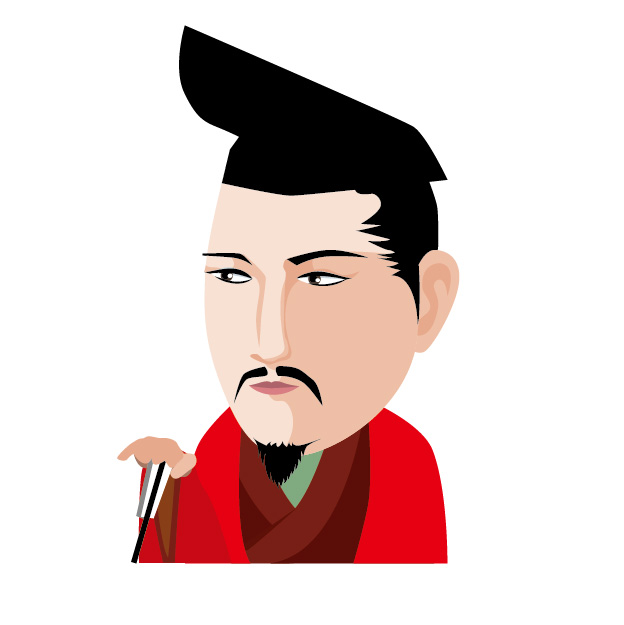
源頼朝 源義経
1185年 長く続いた源平合戦が終結しました。
この戦いで源頼朝は、大義を持って、常陸佐竹氏・木曽義仲・平氏一門等を敵対勢力に認定して倒し、その領地を没収し中立武士に与え、自勢力に取り込むことで力を増していきました。
また頼朝は味方の大勢力である、下総氏や甲斐源氏等をも粛清して弱体化させ、類まれな戦略能力を発揮し、武家の棟梁の地位を盤石にしたのです。
その一方で頼朝の弟、源義経は兄の代わりに最前線で戦い、拙速を持って相手の虚をつく奇襲攻撃、また緻密な現地の情報収集、さらに四国豪族や熊野水軍等を調略して味方につけるなど、戦場において高い戦術能力を発揮して大功をあげました。
源平合戦集結後、朝廷は神器の紛失と安徳天皇の死を大きな問題にしませんでした。頼朝は出世し公卿となり、義経は公卿の一歩手前の伊予守、さらに後白河法皇の親衛隊長に任じられます。
ところが意気揚々と凱旋した義経を待ち受けていたのは、東国豪族の梶原景時等からの独断専行に対する批判でした。実際に義経は戦場で拙速を重視し、屋島や壇ノ浦の合戦で東国武士団の合流を待たずに攻撃を仕掛け、東国武士たちから不満が出ていたのです。
梶原景時曰く、義経は〝平氏を包囲降伏させ、安徳天皇と三種の神器を京へ戻せ〟という頼朝の命令を無視したため、命令に失敗したというのです。思いもよらぬ批判を受け、義経は鎌倉に残らず京へと戻っていったのです。
一方、京において義経に対する後白河法皇からの評価は高く、世間では義経こそ頼朝の後継者にふさわしいという声が聞こえていました。
このことが頼朝・義経の関係をこじらせます。すでに頼朝には嫡男の頼家(よりいえ)がいたため、このままでは後継者争いに発展することが危惧されたのです。
そこで頼朝は、義経に鎌倉へ帰還するように命じます。この時頼朝は事を穏便に済ませ、義経を自身の管理下で統制しようと考えていたのです。
しかし義経の脳裏に、過去頼朝が行った上総氏や甲斐源氏等味方の粛清がよぎります。
義経は後白河法皇を後ろ盾に、公家平氏平時忠の娘を妻にして、京で独自の居場所を築いていたこともあり、鎌倉への帰還を拒否したのです。
しかしこの問題はさらに大きくなります。
頼朝が鎌倉に父の義朝の菩提を弔う寺院を建立し、大掛かりな供養を行います。その供養に参列するよう義経に求めましたが、義経がこれを拒否、これを期に頼朝と義経の関係は決裂したのです。
義経の決起と最期

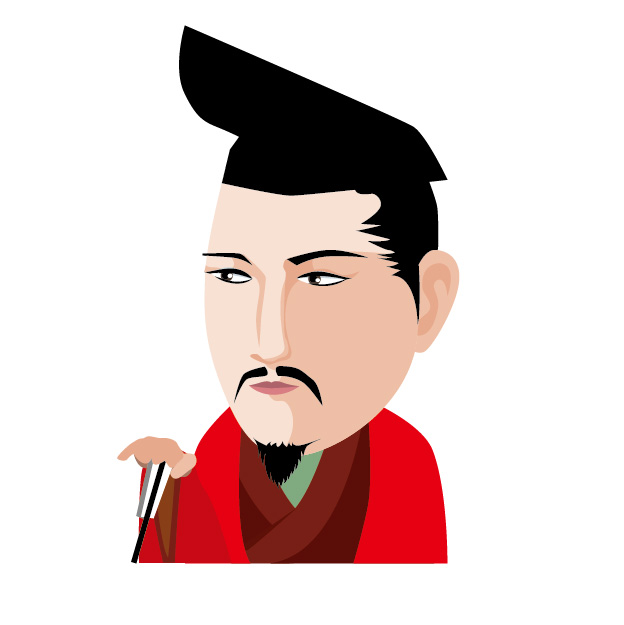
後白河法皇 源義経
京の義経は後白河法皇の下、美濃源氏・摂津源氏と連携し、反頼朝勢力を結成します。この動きに、源平合戦で源頼朝に反したため、政権から疎外された東国豪族たちも加わります。
そして遂に後白河法皇から頼朝討伐の命を取り付けて決起したのです。
この危機に源頼朝はあせることなく、自身に正統性がある事を源氏家人に伝えます。一方で父義朝の供養にも参列せず、主家に対する不義で人望を無くした義経に、わざわざ頼朝と敵対してまで協力しようという武士は少なかったのです。
思ったほど兵が集まらないため、義経は一旦決起を諦めて京から西国で再決起を目指すことにします。
北条時政
東国の頼朝は、京の地理に詳しい北条時政を派遣し、京都守護の任を与えて義経追討を命じます。時政は自身の孫に当たる源頼家のため、義経を徹底的に追い詰めていくのです。
一方で頼朝は朝廷に対し、西国各地に国地頭という、兵糧徴収等に強い権限をもつ、軍政官を設置することを認めさせます。これは西国で平氏残党や義経の反乱を防ぐための処置です。
頼朝は義経に味方した後白河法皇のことを、日本第一の大天狗と非難し、以降後白河法皇に与する武力を、排除することを決意したのです。
義経は九州での再起を目指しますが、船は嵐に合い渡航に失敗し、最後の頼りとなる奥州平泉に向かい、陸上での逃避行を決意します。
その頃、義経に与した摂津源氏や美濃源氏等は、北条時政の追討軍に粛清され、また義経と共に源平合戦を戦った西国豪族も殺害されていきます。
1187年 源義経はたどり着いた平泉で奥州藤原氏の保護下に入ります。この時奥州藤原氏は、源頼朝との対決が避けられないと考えていました。
義経を匿った奥州藤原氏に対し、頼朝は大仏再建を理由に膨大な砂金を要求し、圧力をかけ始めます。
そんな折、当主藤原秀衡(ふじわらひでひら)が亡くなり、秀衡は遺言で義経を大将軍に源頼朝に対抗するよう命じます。
一方頼朝は後白河法皇に義経追討命を出させ、奥州藤原氏にさらなる圧力をかけていきます。ここで奥州藤原氏は義経擁護派と反対派に分かれ、内部分裂が起こります。
この時頼朝はあまり敵を追い詰めすぎると、逆に結束してしまうと考え、じわじわと時間をかけ、奥州藤原氏と義経を分断する離間の計を謀っていました。
その圧力に耐えかねた奥州藤原氏は、わずかな手勢の義経を襲撃し、ついに追い詰められた義経は自刃したのです。
義経は平氏との戦いで見事な戦術で大功を挙げましたが、戦略家頼朝との争いでは、戦わずして敗れ、悲劇の英雄としての死を遂げたのです。
奥州合戦勃発
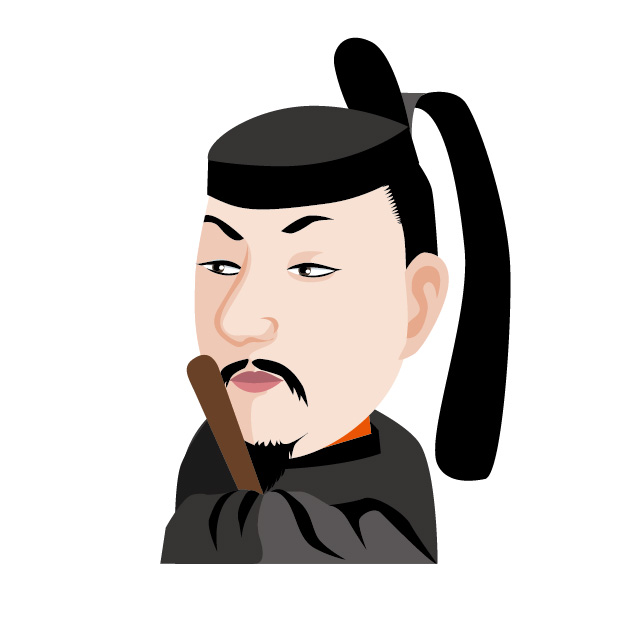
朝廷は義経の死により争いは集結したと考え、奥州追討の命は出しませんでした。しかし源頼朝は、残る大勢力奥州藤原氏の存在を認めたくありませんでした。
唯一の官軍を自称する頼朝にとって、奥州藤原氏は強大な敵対勢力であり、どうあっても容認できなかったのです。
1189年 奥州合戦が勃発し、源頼朝の最終戦争に向かいます。この戦には日本全国から武士が集められ、西は九州の薩摩、さらに東国で敵対していた佐竹氏までも含め、総勢17万の大軍団を結成されます。
源頼朝は後白河法皇を後ろ盾に奥州藤原氏を敵対勢力とし、旧平氏家人たちを自らの勢力下に統一したのです。
遠征軍は頼朝と畠山氏が下野国(栃木県)から入り、千葉氏等は常陸国(茨城県)から、比企氏等が越後からと三方向から、一気に攻め込む大規模軍事行動となります。頼朝自らの出陣は旗揚げの1180年以来となります。
奥州藤原氏とは阿武隈川付近で戦となり、畠山氏等を中心に波状攻撃を仕掛け撃退します。さらに三浦氏や和田氏等が阿津賀志山防塁を攻めて陥落させます。そのことを知った奥州藤原氏は逃亡を図り、頼朝軍は多賀国府に集結し、奥州藤原氏の行方の捜索に入ったのです。
頼朝軍は捜索を続けながら平泉へ入りますが、すでに奥州藤原氏の手で館に火が掛けられ、きらびやかな平泉の都は灰になっていたのです。しかし幸いなことに中尊寺・毛越寺・
大長寿院などの寺社の多くは無傷でした。
平泉制圧後しばらくして奥州藤原氏の当主が殺害され、頼朝は念願の天下を得て、背後の敵がいなくなった頼朝は、ついに念願の上洛を果たすことができるようになったのです。
源頼朝の上洛

1190年 上洛を果たした源頼朝の武者行列は、その規模の大きさで貴族たちの度肝を抜いたとされています。(先頭を畠山氏、中軍に頼朝と御家人、後軍を原氏と千葉氏が努めた。)
そこで頼朝は後白河法皇とおよそ30年ぶりの対面を果たすことになります。
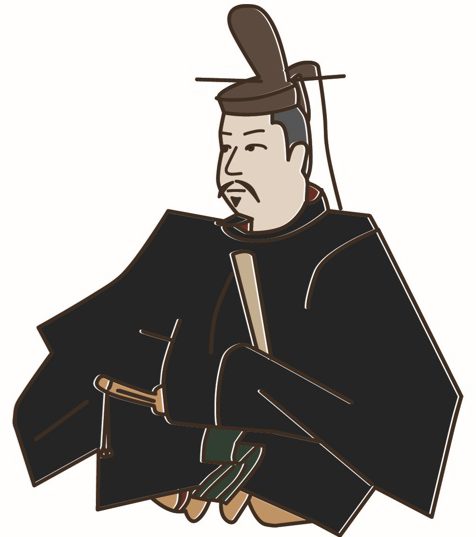
後白河法皇 源頼朝
源頼朝は後白河法皇と会談し、次に後鳥羽天皇に拝謁します。そこで頼朝は王権を支える官軍であることを世間に示したのです。
また、頼朝は藤原氏の九条氏と面談し、九条氏を摂政として支援する協力体制を構築します。また戦時下の〝新恩給与〟(戦で奪った地を家人に与える)に変わる、新制度について話し合ったとされます。
頼朝は公卿である権大納言に任じられ、和田氏・三浦氏・比企氏・梶原氏・千葉氏、他10人の家来に朝廷の官職が授けられます。そして頼朝等は鎌倉に戻ったのです。
1192年 後白河法皇が崩御されます。源氏と平氏の間で翻弄されながら、最後は王権を確立した、波乱万丈の生涯を遂げられたのです。頼朝は鎌倉で後白河法皇の死を悼んだとされます。
同年に頼朝は朝廷から大将軍に任じられます。朝廷は大将軍の上の冠として、征東は木曽義仲が、惣官は平宗盛が任じられ滅亡していたため、不吉として坂上田村麻呂にならい征夷大将軍が選ばれたとされます。
以後征夷大将軍に仕える家人のことを、敬称を付け〝御家人〟と呼ぶようになります。さらに新制度に大犯三箇条が定められ、守護に三つの権限が与えられます。
権限の二つは、謀反と殺人に対する検察権と断罪権です。そして三つ目は大番役を守護が任じる事になりました。頼朝は大番役(京や鎌倉での警護役)を御家人の義務とし、源氏家人(御家人)に限定したのです。
また、頼朝は平時の御家人統制のため、朝廷の官位を活用します。官位は全国共通の肩書で、武士社会で権威を発揮していました。これまで武士たちは官位を得るため、貴族との人脈づくりに精を出していたのです。
しかし頼朝は頼朝の推挙がなければ、朝廷から官位を受けてはならないと定めます。この官位推挙権によって、御家人を統制しようと考えたのです。
これらのことから名実ともに幕府が成立し、国家の武力(軍事警察権)を鎌倉幕府が独占したことで、内乱の時代が終息したのです。
院政から武家政治への移行
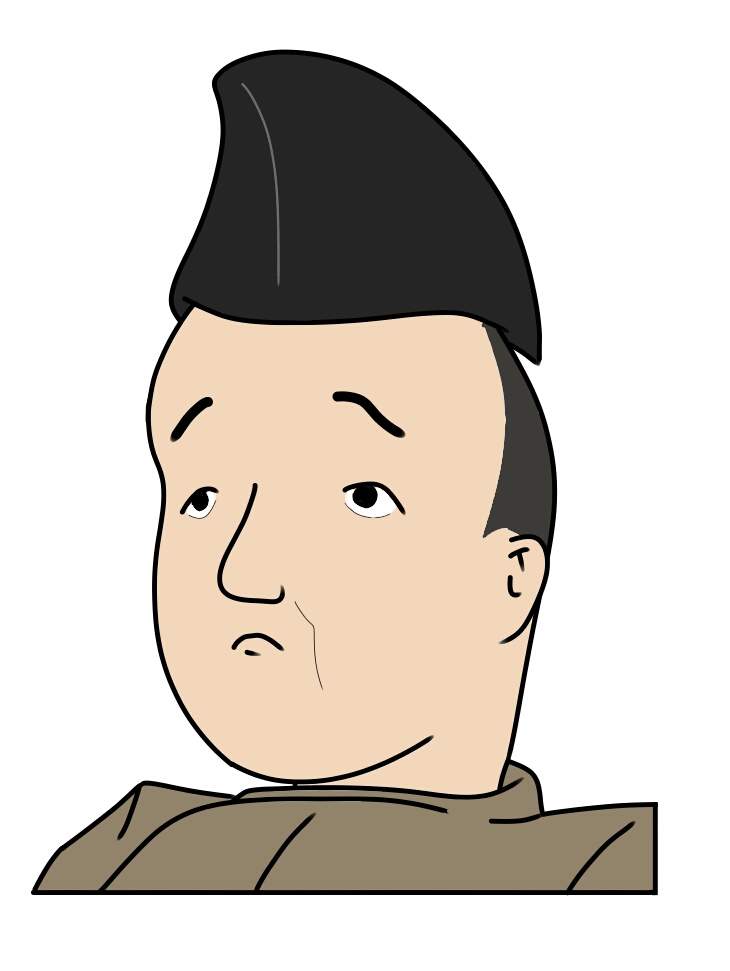
崩御された後白河法皇の孫の後鳥羽天皇はまだ13歳だったため、源頼朝と関白九条氏が政治の実権を担うことになります。
鎌倉幕府成立後、政治の中心は鎌倉に移り、それに伴い重要祭事が鎌倉の鶴岡八幡宮で行われるようになります。
鶴岡八幡宮
源氏の先祖源頼義が京から分霊を移して始まった八幡宮は、1180年頼朝挙兵時に現在の位置に移され、以後放生会(殺生を戒める宗教儀式)や流鏑馬(馬に乗って矢を射、魔を払う天下泰平のための神事)、相撲、舞楽などが行われるようになる東国の社会的中心の場となりました。
特に流鏑馬は盛んにおこなわれ、鶴岡八幡宮に奉納するために作られた国宝・黒漆矢は破魔矢の起源とされています。(鎌倉国宝館に収蔵)

頼朝の晩年と十三人の合議制
1192年 北条政子は頼朝の子、後の実朝を授かります。頼朝は晩年(46歳)で授かった実朝に深い愛情を注いだとされます。
実朝の乳母は北条氏が努め、祖父に当たる北条時政が全面的にバックアップして祝賀を行いました。
この時期に頼朝は弟 範頼を謀反の罪で処刑します。これは頼朝が鷹狩を行った際に、刃傷事件に巻き込まれ、これが範頼の計画によるものとされたためです。
この事件については諸説ありますが、源頼朝の後継者はまだ幼少の源頼家で、御家人たちの中では、合戦の経験が豊富な弟の源範頼の方が後継者にふさわしいのではという意見があったとされています。不明とされていますが、火のないところには煙が立たないかもしれません。
さらに同時期に、源氏一門で最も大きな勢力を持る、甲斐源氏安田氏が些細な罪により謀反の嫌疑をかけられて、処刑されてしまいました。
これらのことがあって、結果的に源頼朝の後継者、源頼家の地位は盤石になったのです。
1195年になると 源頼朝は再び上洛し、源平合戦で焼失していた、東大寺大仏殿の再建を行いました。
また、旧平氏勢力が残っている九州を統治するため、有力御家人の大友氏を赴任させました。大友氏は、島津氏や少弐氏等と共に、九州御家人のまとめ役となったのです。

1199年 源頼朝は病で亡くなります。享年53歳でした。
朝廷に二代将軍 源頼家の後継が認められ、鎌倉幕府の存続が無事公認されました。
しかし、頼家はまだ18歳で戦の経験もありません。そのため御家人たちの中の重臣13人による、〝十三人の合議制〟によって、政治が行われることになりました。
新仏教の誕生
鎌倉時代、時代の大きな変化と共に、仏教が発展しました。
平安時代に国家を守る役を担う国家仏教として、天台宗(延暦寺)と、真言宗(東寺)が存在していました。その役割は寺社の建立と、国家と皇族・貴族のための神事を行う事でした。
しかし、社会の転換期となった鎌倉時代は、武士と農民の存在感が大きくなる時代です。彼らは長く続いた戦乱に不安を抱き、救いを求めて新たな仏教を求めたのです。
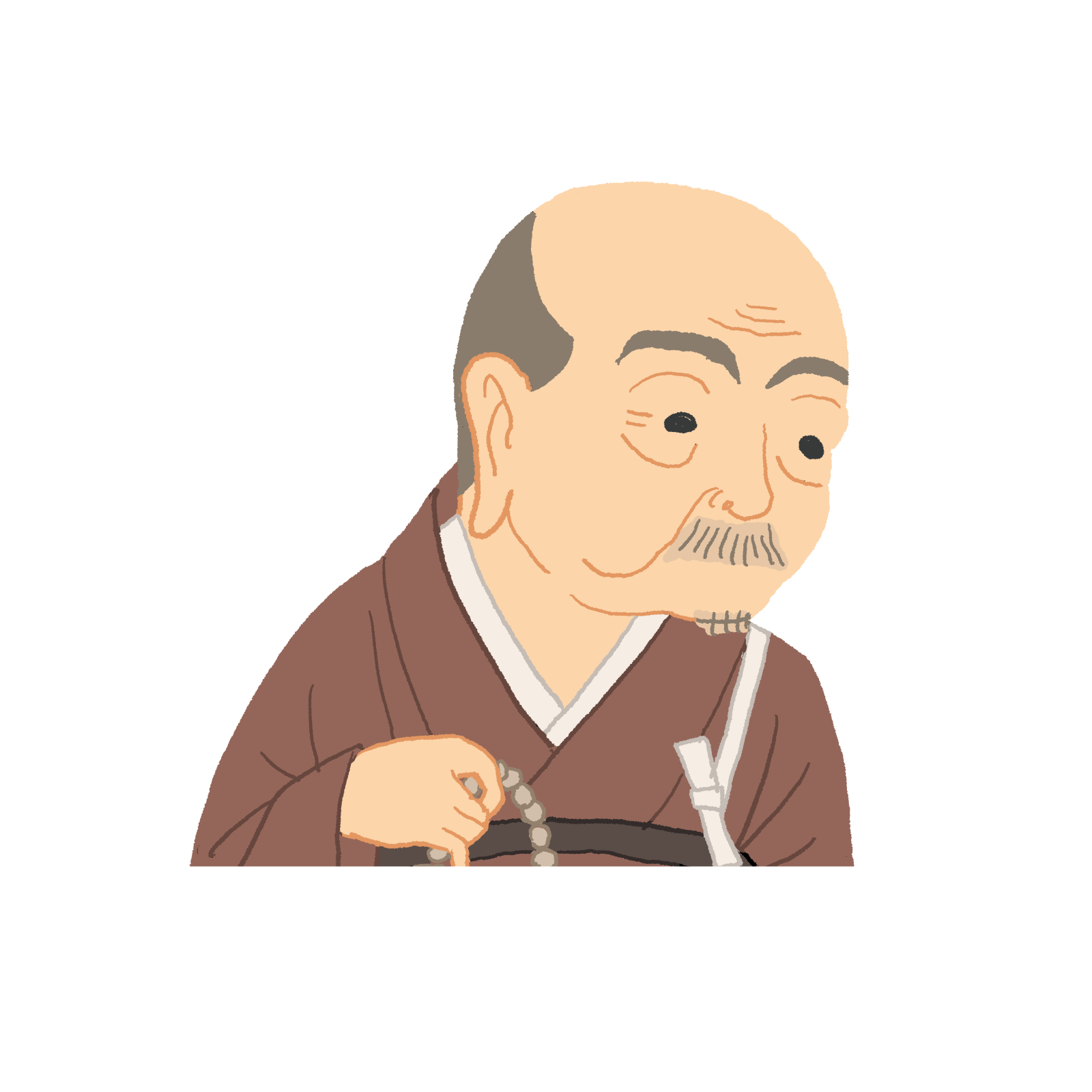
このもとめに応えるようにして新仏教が誕生しました。まずは浄土宗です。開祖の法然(ほうねん)は、比叡山延暦寺で修業し、悟りに達しました。
法然は比叡山を降りてから、「厳しい戒律を守ったり、難解な教義を学ばなくても、日常生活と共に信仰を行い、南無阿弥陀仏(念仏)と唱えれば、皆が救われ極楽浄土にいける」と説いてまわりました。
しかしこの教えは、旧来からの寺社勢力から反発されて、法然は讃岐の地に流刑とされてしまいました。しかし後に京に戻ることを許されて、最後は東山大谷の地で亡くなりました。
法然の死後も浄土宗の教えは広がりを見せ、鎌倉でも民衆に広まります。そして多くの寺院が建立されることになったのです。
法然の拠点は京の東山にあり、浄土宗の中心地として、長く布教活動が行われました。この地に法然の廟が作られ、現在浄土宗総本山〝 知恩院〟として知られています。
知恩院 京都観光ナビ ホームページ
知恩院は浄土宗の開祖、法然上人が入寂された遺跡に建つ京都の由緒ある寺院です。
京都・東山の華頂山のふもとに、大小数多くの伽藍がひろがる、浄土宗総本山知恩院の壮大な佇まいは、厳粛な中にもおおらかな雰囲気をたたえ、お念仏のみ教え発祥の地にふさわしく人々を迎え入れてきました。

山門は徳川将軍秀忠公の建立で、24mもの高さを持つ国宝です。法然上人の御影(みえい)を祀る「御影堂(みえいどう)」は徳川将軍家光公の建造による壮大な伽藍で国宝です。
また、知恩院には古くから伝わる七不思議があり、方丈庭園に七不思議を巡るルートがあります。

武士に広がりを見せたのが、禅宗の臨済宗です。
開祖 栄西(えいさい)は、比叡山延暦寺で天台密教を学ばれました。
栄西は二度(1168年、1187年)中国の宋に渡り、学んだ禅宗を日本に伝えようとします。しかし、旧来の仏教が根付いていた京での布教を断念して、鎌倉で布教を始めました。
臨済宗(禅宗)は座禅を組み、師から与えられた問題を考え抜くことで、悟りに達するというもので、今に集中する不動の心の教えは、武士の気質とあい、武士を中心に広まりをみせました。
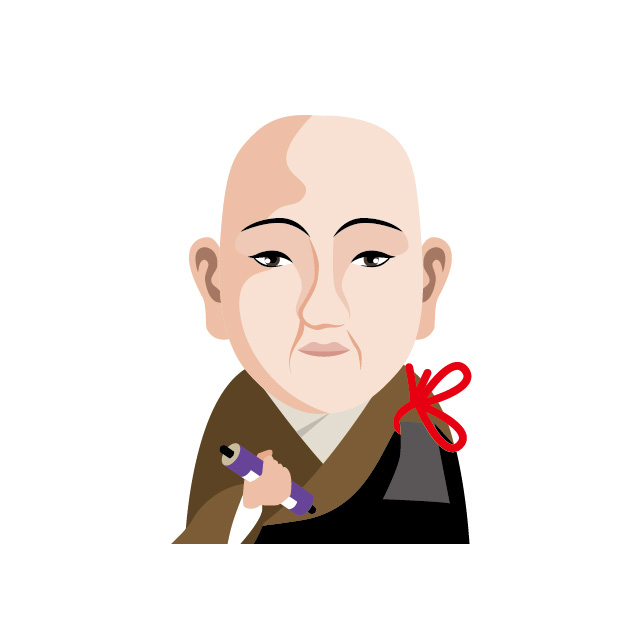
1200年に北条政子(ほうじょうまさこ)が、源頼朝の一周忌として栄西を招きました。そして頼朝を弔うために寿福寺を建立して、栄西が住職となります。
寿福寺
神奈川県鎌倉市扇ヶ谷にある臨済宗建長寺派の寺院で、鎌倉五山第3位の寺院。この地は源氏の先祖源頼義が東北の乱、前九年の役に出陣する際、戦勝祈願を行った〝源氏山〟を背にした地で、頼朝の父・義朝の館があった場所でした。
門をくぐると鎌倉随一と言われる石畳の美しい参道がお目見えします。
頼朝の妻政子が建立した頼朝の菩提寺であり、敷地内に北条政子と三代将軍実朝の墓とされる五輪塔があります。
北条政子と二代将軍頼家は、栄西のことを精神面で頼りにしていたとされています。
そして将軍頼家の支援により、京に臨済宗大本山 建仁寺が建立されたのです。
これ以後、朝廷に親密な天台宗・真言宗に対し、臨済宗を〝幕府のための仏教〟として位置付けられたのです。そして栄西は、武家政権の相談役的な存在となっていったのです。
建仁寺写真:京都府フリー素材写真集 https://photo53.com/kenninji1.php
建仁寺 京都観光ナビホームページ
建仁寺は臨済宗建仁寺派の大本山で、建仁2年(1202年)に開創しました。開山は栄西禅師、開基は源頼家です。
当時の元号を寺号とし、室町幕府により中国の制度にならった京都五山が制定された際は、その第三位として厚い保護を受け大いに栄えます。
しかし戦乱と幕府の衰退により一時荒廃しますが、徳川幕府の保護のもと堂塔が再建修築されました。

建仁寺では禅寺体験として座禅や写経などの体験を行っています。また、国宝 風神雷神の屏風絵や、法堂の天井絵双龍図が有名です。
御家人同士内乱の時代
二代将軍頼家の時代は、御家人同士の激しい内乱が起こりました。
まず最初に起こったのは、源頼朝の腹心だった梶原景時(かじわらかげとき)の事件です。
かつて源平合戦で源義経を陥れたとされる梶原景時は、重臣で高い政治力を持っていた、結城朝光(ゆうきともみつ)を讒言で陥れようと画策しました。
しかし御家人たちは、この件を調べあげて激しく追求し、ついに梶原景時は失脚し、梶原氏は滅亡したのです。
忠臣の梶原景時を失ったことは、将軍頼家にとって大きな打撃となりました。
さらに最有力御家人の、比企氏と北条氏が衝突しました。
源頼朝は生前、両家の仲を取り持つよう働きかけていましたが、それがかなう前に亡くなってしまっていました。
二代将軍頼家の縁戚で、〝頼家派〟の比企氏に対し、北条氏は源実朝(頼家の弟)を支持していました。
ある時、将軍頼家が病で危篤になった際に、家督争いが勃発したのです。〝頼家派〟の比企氏と、〝実朝派〟の北条氏が、幕府を二分する家督争いを起こしました。
その争いを制したのは北条氏でした。この争いによって将軍頼家と比企氏は失脚し、三代将軍として源実朝(みなもとさねとも)が擁立されたのです。
失脚した源頼家は北条政子の命令で出家し、その後23歳の若さで亡くなっています。
北条時政の専横と失脚
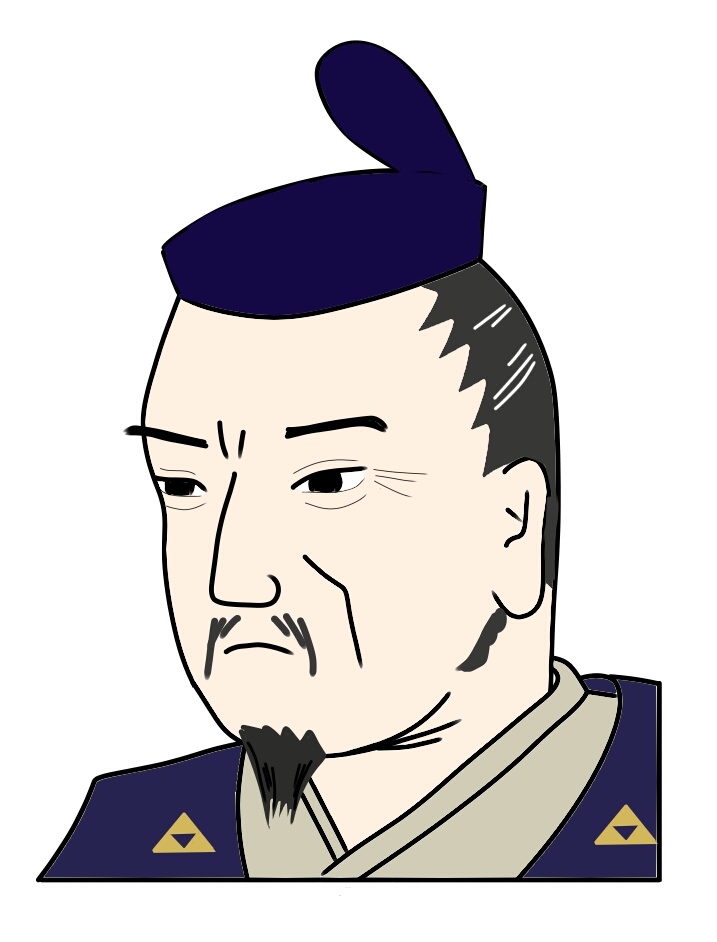
鎌倉幕府の実権を握ったのは、北条氏の当主北条時政(ほうじょうときまさ)です。
さっそく時政は、御家人の有力者だった、畠山氏に謀反の嫌疑をかけて、滅亡させます。
畠山氏と義理の兄弟関係にあった時政の子、北条義時(ほうじょうよしとき)は、これがきっかけで父時政と対立するようになりました。

北条義時
さらに専横なふるまいを行う北条時政は、自分の娘婿で源頼朝の養子の 、平賀朝友(ひらがともまさ )を四代将軍にしようとして画策します。
窮地に陥った三代将軍実朝を救ったのは、母の北条政子でした。
政子は三代将軍実朝を救出し、北条義時が北条時政の勢力を駆逐して、時政は伊豆で出家し隠居することになったのです。
北条時政は源頼朝と共に旗揚げした重臣でしたが、最後は策に溺れて失脚したのです。
鎌倉幕府はこれから北条義時と北条政子、そして重臣大江氏や・安達氏らによって運営されていくことになるのです。
御家人たちの反発
始まった北条氏による〝専制政治〟を不服として、御家人たちは反発しました。
有力豪族で侍所別当(軍事・警察の最高職)をつとめる和田氏が挙兵しました。しかし、和田氏は、共に行動した三浦氏の寝返りによって、北条氏との戦いに敗れました。
これ以後北条義時は、政治の政所別当と軍事の侍所別当を兼ねる〝執権〟として、鎌倉幕府を運営していくことになりました。
荒れる幕府ではありましたが、三代将軍実朝は京の華やかな文化に魅入られていました。
京では成長した後鳥羽上皇が〝新古今和歌集〟の編纂を命じ、華やかに和歌文化が広まっていたのです。
新古今和歌集の特徴は、優雅で繊細、情緒的だったとされ、この時代は最も和歌が盛んだったとされています。
このような文化に魅入られた実朝も、貴族藤原氏に弟子入りするなどし、後鳥羽上皇との親睦を深めていったのです。
後鳥羽上皇が詠まれた和歌は、〝奥山の おどろが下も 踏み分けて 道ある世ぞと 人に知らせん〟(たとえ奥山の藪の中に分け入ろうとも、必ず希望の道があることを人々に知らせたい)です。
後鳥羽上皇は〝和歌は世を治め 民をやはらぐる道である〟とおっしゃられたとされ、文化力で治世を行おうとされたのでしょう。
和歌や蹴鞠、琵琶の他、弓馬にも優れる文武両道だったとされる後鳥羽上皇は、まさに英雄の資質がある人物だったと考えられます。
源氏将軍家の滅亡
1219年 将軍実朝が突如暗殺されました。
この事件の首謀者とされるのは、二代将軍頼家の子公暁(くぎょう)です。その公暁も、暗殺直後に討ち取られてしまい、源氏将軍家は、わずか三代で滅亡してしまったのです。
この事件について真相ははっきりしていませんが、これまでに起こった多くの抗争の結果として引き起こされた事件と考えられます。
三代将軍実朝と親しくされていた後鳥羽上皇は、この事件に不信感をもたれたとされています。後鳥羽上皇は幕府の混乱の原因が、北条義時にあると考え、敵意をもつようになっていくのです。
後鳥羽上皇
北条義時は後鳥羽上皇の皇子を、四代将軍として迎え入れようとしますが断られます。後鳥羽上皇は、権威を北条氏に利用されることを嫌ったと考えられています。
後鳥羽上皇との話し合いが決裂したため、北条政子が源頼朝の姉の〝ひ孫〟にあたる、藤原氏の最高貴族九条三寅(みとら)を、未来の将軍として鎌倉に迎えました。
三寅はこの時わずか二歳のため、北条政子が後見人として、実質的な将軍になります。これが世に言われる〝尼将軍〟です。
後鳥羽上皇は、自身の荘園(私有地)の権限を拡大するために、かつて源頼朝が任命した
一部の地頭(土地や税収を管理する役)を罷免しろと幕府にせまりました。後鳥羽上皇は幕府の混乱を好機と捉えて、幕府の弱体化を図って動き始めたのです。
この命に対し、北条義時は〝頼朝公が任命した役は理由なく解任できない〟として、はねつけました。
承久の乱勃発
1221年 仲恭天皇の命として〝北条義時追討の命〟が下されました。
後鳥羽上皇はこれは〝倒幕〟ではなく、あくまで北条義時の謀反に対するものだとしました。〝天皇の権威を忘れ、傀儡の幼将軍を思うがままに操る北条義時の謀反〟と断罪し、御家人たちの分断による弱体化を狙ったのです。
一方、鎌倉幕府では北条義時と政子を中心に対策会議が開かれました。〝朝敵〟となる事を恐れる御家人たちに対し、尼将軍の政子が熱烈な演説を行ったとされています。
〝頼朝の恩は山よりも高く、海よりも深い。道理から外れた命に従わず、源氏三代の将軍が残したものを守りなさい〟
北条義時は、嫡男の北条泰時(ほうじょうやすとき)を総大将とし、源氏一門の足利氏らを従えて京へ出撃します。
この戦は北条義時が、後鳥羽上皇の無理難題から御家人を守ろうとしたところから始またっため、その挙兵によって義時の名声は大きく上がる事になりました。
幕府と源氏を支持する多くの武士たちが加わり、幕府軍は一気に膨れ上がります。圧倒的な〝19万の大軍勢〟となった軍が京へ攻めのぼったのです。
まさか攻めてくるとは、思いもよらなかった朝廷は、あわてて出兵して宇治川で幕府軍と対峙しました。しかし、幕府軍の佐々木氏が決死で宇治川を渡り朝廷軍を打ち破り、あっというまに都を制圧してしまったのです。
これにより後鳥羽上皇は、隠岐中ノ島へ流罪とされてしまいました。中ノ島では仏への信仰と和歌を詠む日々を過ごされ、京へ戻る事はかないませんでした。
足利一門の発展
また、この戦で大活躍を見せた、源氏足利一門は、関東の他、京と鎌倉の中間の重要地点である、三河を領地として与えられることになりました。三河の足利氏は、地名である〝吉良〟や〝今川〟を名乗るようになります。
さらに足利氏当主は、代々北条氏から正妻を迎えていたこともあり、大いに発展していくことになっていくのです。
承久の乱後、朝廷が持っていた領地や権限はすべて幕府に奪われることになり、朝廷は実質的に幕府に従属することになったのです。
そして京に鎌倉幕府の出先機関が設置されます。六波羅の北と南に〝六波羅探題〟が設置され、北条義時の子泰時と、弟の時房を京に駐留し、朝廷の動きを監視することになったのでした。
次の話
10分で読める観光と歴史の繋がり 親子二代で日本の武士を一つにまとめた北条時頼と時宗、異国からの侵略者 元寇 これぞ武士の誉れ /ゆかりの古都鎌倉の寺院 高徳院(鎌倉大仏)、建長寺、明月院
興味のあるかたはこちらもどうぞ!
中部観光ホームページ 歴史と共に巡る旅(鎌倉大仏、鶴岡八幡宮、明月院、建長寺)

コメント