
SDGsは持続可能な社会を実現するための17のゴールを設定し、そこにいたるまでに169のターゲットとして方向性や手法を示しています。
SDGs活動では、ゴールに至るまでのストーリー(物語)を描いた方がいいと思います。つまり『私たちは持続可能の目標実現(17の目標のいずれか)に向けて、このような準備をし、このような活動を行っています』と表すことで、自分(自社)オリジナルなSDGsの活動になるということです。
今回はSDGsのストーリーを描くための材料となる〝点〟となる部分をメモ書き風に書いてみたいと思います。何かしら、ストーリーを描く時のヒントとなるかもしれません。
今回は目標7から11までをメモしたいと思います。
※あくまでメモのため、詳細は個別に確認ください。また、新しい情報があれば追記する場合があります。
7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに
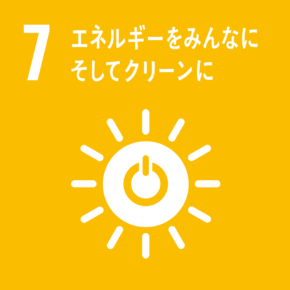
目標7は、ざっくりいうと、エネルギー問題と、環境問題です。
世界で〝地球温暖化〟は共通ワードになっています。
そもそも、地球は太陽からの熱によって常に温められています。本来その熱は、地上から宇宙へと放出されているのですが、温室効果ガス(主に二酸化炭素やメタンガス)がその熱を取り込んで地上に残る事で、温暖化現象が起こっています。
地球温暖化というのは、19世紀の〝産業革命〟を起点として考えられています。そのため、産業革命以前から比べて、気温が何度上がったという風に言われています。産業革命の時に一気に進んだ、石炭等の火力エネルギーへの転換が、温暖化の大きな要因となったという訳です。
火力エネルギーというと〝発電〟が思い浮かびます。以下は三種類の火力発電の特徴です。
①石炭火力発電は、コストが安く発電力が安定しているため、発展途上国等で重宝されています。温室効果ガス排出は最も多いですが、備蓄しやすいというメリットがあります。
②天然ガス火力発電は、三種類の中で最も温室効果ガスが少ないです。しかし石炭・石油よりも輸送手段が難しく高コストになり、しかも備蓄しにくいという課題があります。
③石油火力発電は、石炭より温室効果ガス排出は少ないのですが、コストは一番高く、また輸入できる国(中東等)が限定されます。しかし備蓄しやすいというメリットがあります。
火力エネルギーの輸入・輸出に関して、アメリカはシェールガス開発の成功によって、ガス価格は大きく引き下げられるようになり、エネルギー輸出大国となりました。これによって世界のエネルギー市場に、大きな影響を与えるようになっています。
(コロナ禍の影響により、各国エネルギー戦略による価格変動は激しいですが。)
日本もシェールガスを積極的に輸入することで、温室効果ガスが少なく、さらにコストが安くて安定している〝ガス火力発電〟を主力にすることができるかもしれません。
しかしシェールガスは、採掘時にメタンガス(温室効果ガス)を放出すると言われているため、二酸化炭素削減効果と、メタンガス排出増化の影響は微妙なところです。
欧州と中国では、水力・風力・太陽光発電に積極的に取り組んでいます。
特に中国は、広大な国土が強みで自然エネルギー発電の分野では、世界トップと言われています。もし今後効率よく発電がまかなえるならば、石炭等の資源輸入に頼っている現状を脱却し、資源不要・低コストで、かつ枯渇の可能性がない発電が可能となります。
しかし自然エネルギー発電は、発電量自体が自然の影響を大きく受けます。特に日本は、国土が狭い事や、台風や雨等の気象の影響も受けやすく、風や気象が安定しているヨーロッパ等と比べると、現状はあまり安定していないようです。(日本では海洋風力発電の取り組みに期待。※目標14で紹介。)
そのかわりに日本では、石炭火力発電の技術革新が進んでおり、世界でトップの高効率の火力発電が可能です。非効率な石炭火力発電技術しかない発展途上国に対し、高効率な石炭火力発電技術を輸出する事で、間接的に温室効果ガス削減に貢献してきたと言えます。
しかし、そもそも石炭火力発電が原子力・ガス火力・自然エネルギー等と比べると、温室効果ガス排出量が多いことで、国際的に批判を浴びています。
エネルギーにはつきものの〝温室効果ガス〟は、気候変動による問題(目標13)に直結してくることになります。
それではここでいくつか希望がもてる、各国の取り組みについてご紹介します。
ドイツのフライブルクでは、古い建築物の断熱工事や〝コージェネシステム〟による一般住宅で可能な温室効果ガス削減策に取り組んでいます。
これは〝発電〟と同時に発生する〝熱〟を有効利用するもので、熱によって蒸気や温水をつくり、暖房や給湯に活用する仕組みです。(これまでそれらの熱は廃棄されていたそうです。)
これにより夏の間に蓄電し、冬に暖房や温水として活用することができます。フライブルクでは各家庭の暖房製品取り換え時に、行政がコージェネシステム導入を支援しています。
また、注目されているのが、IOT(インターネット・オブ・シングス=家庭や物流や製造をインターネットシステムで直結させること)の、エネルギー版 IOE(インターネット・オブ・エナジー)です。
これはAⅠやビッグデーターを活用し、再生可能エネルギー、つまり自然エネルギーを、効率よく管理する仕組みです。
もともと自然エネルギーは天候や災害に左右されるため、需要と供給が不安定で無駄も多いという弱点がありました。(蓄電池も時間によって消耗してしまうという弱点があります。)
しかしIOEにより、需要予測や気象データーを解析し、最適な量の発電を行うと共に、蓄電も含め、供給不足や需要過多が起こらない様にコントロールされていきます。この技術により、再生可能エネルギーの不安定さを解消しようということです。
なお、IOEの活用予測の身近な例で、スマートフォンや電気自動車を、無線により適切なタイミイングで自動充電されるようにする事なども検討されてます。
もう一つ余剰電力については、電力を〝水素〟に変える技術があります。これがP2G〝パワー・トゥ・ガス〟です。余剰電力を使って、水を水素に電気分解するということです。
水素は電気よりも備蓄が簡単で、天然ガスの資源として使用することができます。また、水素は、車の燃料としても活用されています。トヨタの〝ミライ〟や、海外のアウディ・〝トロン〟などです。
ミライは、車内タンクの水素と空気中の酸素との化学反応によって電気をつくり、そのの電力によって走行しているのです。さらに緊急時にはその電力を、外部給電が可能で、住宅家電に仕えるため、災害時の発電機としての使用も可能です。
アウディ社では、自然エネルギーで生成した水素と二酸化炭素を化学反応させ、メタンガスを製造しています。
それを資源とする天然ガス〝イー・ガス〟を製造して、それをエネルギーとするトロン(天然ガス車)を世に出す事により、温室効果ガス削減に貢献しているのです。(つまり温室効果ガスそのものの二酸化炭素を、天然ガスに変えているということ。)
水素以外に、電気自動車の取り組みがヨーロッパを中心に進んでいますが、〝電力消費の増加〟が懸念されています。
現状でエネルギーの問題は、〝走りながら課題を解決している状態〟で、何が正解なのか、はっきりしない部分が多いと感じられます。
最後に、自然エネルギーには大きな可能性があります。それは〝地方創生〟です。自然界には風力・水力・地熱等、昔からあるエネルギーがあります。
日本の地方で昔からある自然エネルギーを上手く活用している地域があります。温泉の地熱を利用した発電、そのお湯を使って養殖事業、豊富な木を活用した木質チップでバイオマス発電、地域共同で小水力発電を行う等、多くの成功例が見受けられます。これらの多くはエネルギーの地産地消によって地域産業の発展に貢献しています。
また、地方の漁業で大きなコスト負担となっているのは船の燃油で、世界の燃油の高騰によって今後持続できなくなる可能性があるといいます。しかし現在開発中の〝ソーラー船〟(太陽光発電の船)の運用が軌道に乗れば、大きなコストダウンとなり、漁業の持続可能な未来が開けます。
エネルギー分野は日進月歩で、今後のテクノロジーの進化に期待したいところです。
8.働きがいも経済成長も
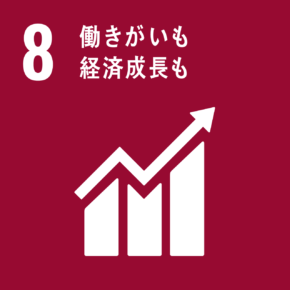
目標8では持続可能な〝経済成長〟と、〝働きがい〟という二つのテーマが存在しています。経済成長については、経済成長と環境保全を両立させるという大きな課題があります。
地球に住み続けられるように、自然資源を守るために、原始的な生活に戻るのは現実的に難しいです。
テクノロジーのない原始的な生活は、貧困や食料難の問題を大きくし、それに伴う政治の混乱から、戦乱・テロが増加する可能性があるからです。
なんだかんだいって資源・技術・法規のバランスが取れた、安定した生活が、平和を保つための鍵ではないかと思います。
経済と環境をどうやって両立させるかという事を、持続可能の観点で考えると、自然資源の回復力を消費が上回らないということが大切です。
世界のあらゆる〝資源〟は有限であり、現代は豊かな生活のために、未来の子孫たちの資源を使い込んでいると考えられるからです。
例えば物を大切にする(消費を減らす)という事は、今後世界で広まっていくかもしれません。
そうなると、〝使い捨て〟が当たり前だった産業では、〝長く使える〟ものが求められるようになり、ものづくり企業は、生産よりもメンテナンスやリサイクル・リフォームといったサービスが必要とされてくるかもしれません。
例えば、家のリフォームの様に、衣類もデザインを直してくれるサービスがあると面白いですね。
ヨーロッパでは、住宅をリユース(再利用)するために、ばらして使えるような木材建築に転換するようです。木材は断熱性に優れ、温暖化対策にもいいようです。
このような資源循環型ビジネス(サーキュラーエコノミー)は、今後ますます発展し、持続可能な経済成長を実現するための、旗手の役目を担っていくと考えられ、今までのビジネスモデルを大きく変換させる、イノベーションとなります。
あらゆるものづくり産業は、生産・消費・保全というサイクルを創ることが重要となってきます。
例えば〝養殖〟で、食産業は天然物がいいよね、という風潮がありますが、魚の減少や人口増加による食糧難を考えると、資源の保全を目的とした養殖は必要不可欠となってくると思います。
もし地域内で生産し、消費し、さらに保全までできるようになれば、資源が尽きる事のない持続可能な地域経済が完成します。
仕入れによってお金が他地域に流れることはなくなり、地域内で消費されることで、地域に豊かさが〝循環〟します。これは地方創生のための〝鍵〟になり得ると思います。
〝働きがい〟という点では、ベーシックインカムとイノベーション(新たな取り組み)が鍵になると思います。
ベーシックインカムを直訳すると〝最低所得保証〟となります。これは国民全員一律に一定額を給付するもので、働いている人・いない人、年齢・性別すべて関係なく一律にです。
子供が多い家庭の方が支給額は多くなり、例えば5人家族位になれば、支給額が月50万円を超えることが予想され、安定して暮らすことができるようになります。
現在〝無給の労働〟に従事している人たちが世界に大勢います。それは家庭内の家事・育児・介護・清掃・水くみなど、生活のための労働です。
(実際に発展途上国では、女性の9割は無報酬労働者と言われています。)
ベーシックインカムは、これらの人たちにやりがいと誇り、自立した生活を与えてくれる可能性があります。
今後の世の中で、仕事はAIとロボットに奪われるという話はとても現実的で、将来的には働きたくても働くことができない人が増加すると予想できます。現在誰もがプロスポーツ選手になりたくてもなれないのと同様です。
ベーシックインカムが成立した世の中では、ワークシェアリングによって仕事が、例えば1日2時間とか、1週間に2日間とか、そういった働き方が当たり前になるかもしれません。
多くの仕事はロボットやAIが担い、人間は生活のための労働や社会貢献活動等を行う社会になるということですが、このような事になると社会の仕組みを大きく変換させなけれならないと思います。
皮肉なことですが、世の中の仕事が無くなることで、現在大きな問題となっている高齢者介護等は解決されていくかもしれません。
また、このような世の中であれば、ゴミ拾い等のボランティア活動が広がり、プラスチックゴミ等の問題が解決していくかもしれません。
一方で芸術・伝統文化・伝統産業、農業、サービス業やアミューズメント産業などが大きく発展する可能性があります。やりたい仕事に従事できることで、その分野での若い方々の活躍の機会が広がる可能性があるからです。
そして挑戦しやすい世の中は、世の中をより良くするための研究やビジネスなど、イノベーションが起こりやすくなる可能性があります。
この様な時代では、好奇心や探求心、そして生きることを豊かにするための創造力が必要となるのではないかと考えられます。
これらはイノベーションに必要とされる力でもあります。
これについては子供たちへの教育に関わってきます。これまでの様に勉強し、大学へ行き、企業に就職するというシステムが成立しなくなるからです。
いかにして新時代に適応できるような、教育システムができるはとても重要となります。
ただ、ベーシックインカムの実現には、財源を始めとして多くの課題があります。財源について、経済成長が必須になると思います。この点については、人件費が抑えられるロボットや、仕事の効率を上げるAIへの期待が高まります。
(ベーシックインカムについては目標10でもう少し付け加えたいと思います。)
9.産業と技術革新の基盤をつくろう

目標9では〝基盤〟つまりインフラ整備の重要性があげられます。
この項目は他の目標とも密接に関わっています。発展途上国においてはインフラ整備によって、多くの課題が解決できると思います。
まずはインターネットの整備です。
アジア・アフリカではインターネット未整備地域が多く、これが産業の発展と知識の共有の妨げとなっています。
しかしながらアフリカのケニアでは、プリペイト携帯電話の普及と共に、電子マネー〝Mペサ〟が一気に普及しました。(発展途上国では銀行が少ないため、電子マネーが普及しやすい傾向があります。また、偽札問題がある国も同様です。)
逆に日本は、銀行やコンビニATMが整備されているため、電子マネーの必要性がやや薄れてしまうのではないでしょうか。ただこれは日本の金融インフラが整っているという事でもあります。
話は戻りますが、発展途上国でインターネットが整えば知識のシェアが起こり、電子マネーの活用と共に産業が一気に発展することが予測できます。それはグローバル企業にとっても、大きなビジネスチャンスとなります。
現在アメリカでは衛星ロケットの打ち上げによって、世界のインターネットの整備に取り組む企業があります。(プロジェクト・カイパー計画・starlink衛星など)
いまや宇宙開発の予算は、国家予算から削られており、民間企業へ委託されているのです。
その企業は、ジェフ・ベゾス氏のAMAZON、そしてイ―ロン・マスク氏のテスラ社、そしてGoogle(の子会社)です。今後宇宙旅行だけではなく、民間企業による宇宙開発事業に期待したいところです。
現在も国際宇宙ステーションへの補給のため、ロケット打ち上げは行われており、ゆくゆくは着陸可能(再利用できる)ロケットの開発を目指しています。
インフラと言えば、イメージしやすいのが〝道路=アクセス〟です。交通網の整備は産業の成長に必須です。
発展途上国では、生産者が作った物を市場に卸す手段がない場合があります。それは輸送手段がないことや、道路の未整備、治安の問題などがあるからです。
そうなると仲介業者が登場します。それが公正な業者なら問題ないのですが、発展途上国では仲介業者による〝搾取〟が起こりやすいといいます。これによって生産者の利益は損なわれ、産業の発展が阻害されることになります。
現在交通インフラは、ODA(政府による国際開発援助)で整備が進んでいます。(ODAについては目標17でふれたいと思います。)
日本では国と民間企業の、共同プロジェクト(インフラ事業)が盛んになりつつあります。理由は〝国際競争力〟を高めるためです。
インフラ事業でよく目にするのが〝新幹線(高速鉄道)ビジネス〟です。この分野はヨーロッパに一日の長があり、世界のビッグ3と言われる企業はすべてヨーロッパ企業で、その3社を合わせると、鉄道車両製造の50%のシェアを持っています。
一方で日本の鉄道には、信頼性の高い車両性能と世界NO.1の定時運行能力があります。しかし、日本は鉄道分野の国際競争力が低いのです。
その一因として〝ガラパゴス化〟した特殊なシステムがあります。
日本は複数の企業によって鉄道システムが構築されているため、単独企業では他国の事情に合わせる事が難しいのです。(この様な問題は、携帯電話でも同じことが起こっていました。)
この問題を解決するために、官民一体となったトップセールス〝オールジャパン体制〟という取り組みが誕生したのです。
日本は今後発展途上国で需要が増える交通インフラ事業に向けて、国家と複数の企業による複合チームを構成しています。
これによって技術開発の発展、特殊技術の秘匿(流出を防ぐ)、そして国家によるトップセールスが可能となります。
それともう一つ、日本の優れた事業運営ノウハウの提供と、メンテナンスサービスという付加価値を付けることが可能となり、ガラパゴス化への対策となります。
これはSDGsで重要視されるている〝レジリエンス(強靭でしなやか)〟の強化であると言えます。レジリエンスなインフラ構築は、〝壊れない、復旧が早い〟という事でもあり、日本に頼めば、導入後も安心というイメージをPRする事はとても大切だと思います。
例えば日本では道路が陥没しても、すぐさま復旧してしまいます。このような復旧技術やシステムは(災害対策等として)どの国でも重宝されるはずです。
日本は安全でレジリエンスなインフラ構築で、世界に貢献できるのではないかと考えられます。
10.人や国の不平等をなくそう

目標10は〝人〟と〝国〟を分けて考える必要があります。
まず〝国〟として考えると、〝発展途上国〟と〝先進国〟の差を少なくするという事があります。
発展途上国では1日2ドル以下で生活している国があり、これを1日2ドル以上で生活できるようにすることが第一歩となります。
解決策の一つが目標8で取り挙げた、べーシックインカム(最低所得補償)です。
これが実現すれば発展途上国に存在する無償労働(家事・育児・介護・水汲みなどの生活労働等を無給で行うこと)が無くなります。
(多くの発展途上国では、女性は無給の為に自立することもできません。)
大きな課題として、①財源をどうするか。②他の補償との兼ね合いをどうするか。という事があげられます。
財源確保には他の歳出を削減する、税収を増やすなどが考えられます。
しかし一部の層において、他の補助(年金・医療費補助・生活保護等)が打ち切られたり、税金が増額された場合に、ベーシックインカムだけでは生活が成り立たない可能性があります。
それでもベーシックインカムによって、多くの人々が貧困を脱出できる可能性があります。
日々の生活がやっとの人たちが、ベーシックインカムを子供の学費に充てる、家畜を買ったり、船や網を買うなどして、収入を増やすチャンスを得られます。
これで生活環境の向上、並びに地域の経済成長につながる期待があります。発展途上国の多くの人々は資金がないために、貧困脱出のチャンスがないのです。
世界の一例として、アメリカのアラスカ州では、住民のほぼ全員が石油基金から、毎年特別配当を受け取っています。これは地域資源の石油で得られる利益を使っています。住民はそれを厳しい自然環境での生活の〝足し〟にしているといいます。
実際に社会実験や国民投票を行ったフィンランドでは、ベーシックインカムの仕組みとして、〝一定額を支給する〟財源として、社会保障費をカットするという計画があります。
一部での社会実験を終え、フィンランドでベーシックインカムが今後どうなっていくかはまだ未定の状況にあります。
また、発展途上国の一部の貧困地域でも、NGO(国際支援を行う非政府組織 )などが試験的なベーシックインカムを行っているそうです。その結果が出るのは、これからという事になります。
〝人〟で考えた場合は、特に先進国において、平等や公正な考えを定着させる必要があります。
これによって差別や偏見の壁を無くし、公正な社会の実現や、柔軟な発想とイノベーションによる社会の発展につながると考えられます。
北欧のスウェーデンでは、学校教育で〝民主主義〟〝投票権〟〝平等と公正〟についての学校教育がおこなわれています。
例を挙げると、学力の不平等をなくすため、学校教育はすべて無償、教科書も修学旅行も給食もです。
また男女平等の考えを根付かせています。そのため、子供たちはお父さんとお母さんの役割は同じという認識を持っています。(お父さんが夜お酒を飲み行くとか、お母さんが家事をするとかのイメージはありません。)
そして若者の選挙投票率がとても高いです。スウェーデンの30歳以下の投票率は80%を越えています。
この理由は民主主義教育にあるといいます。
子供たちの判断を重視し、ルールは上から与えられるのではなく、みんなで話し合って決めるようにしています。このおかげでルールが作られた目的や、意味を知ることができます。さらにルールは社会の変化に合わせて変わるという事を教えています。
そして政治の決定は、私たちに大きく影響を与えるということを教えています。投票によって、私たちも政治に影響を与える事が可能で、政治を決定しているのは私たち(政治は自分毎)である事を教えています。
選挙権は、不公平を正すためにとても大切で、仮に若い人が投票しなければ、若い人の為の政策はつくられにくくなってしまいます。
政治に興味がなかったとしても、投票すること自体がとても大切ということです。
こういった事を教育で学ぶことにより、世界中の不公平や不平等が改善していくきっかけとなっていくのではないかと考えられます。
11.住み続けられるまちづくりを

目標11では、〝安全〟と〝レジリエンス〟という2つのテーマがあります。
〝安全〟に関しては、まず治安があります。日本はだいたいどこにいっても安全で、テロが行われることなど、ほぼありません。
しかし、発展途上国の多くの国ではテロ組織が存在し、生活や産業に暗い影を落としています。
発展途上国はスラム街が増えています。これは人口増加にその一因があります。人が増えたことで、地方に住む若者たちが大都市に職を求めて集まってきます。
しかし、大都市でも仕事は賄いきれず、職のない若者たちがスラム街に住むようになります。そして不満を抱えテロ組織等に加わる若者が出てくるのです。
またある国では、昔は農産物を作っていた農家が、アヘンを栽培するようになっています。街から市場に卸しに行くための安全な交通手段がないため、アヘンを街まで回収に来てくれる非合法組織に卸しているのです。そしてそのアヘンは世界中に広まっていく事になります。
このような現状を変えるために、フェアトレードの重要性が高まっています。先進国のグローバル企業が、搾取のない公正な取引を行い、設備や環境に投資することで、発展途上国に安定した職と生活を提供することができます。
グローバル企業には、より質の良い品が納入されるようになり、企業のイメージアップにつながり選ばれる企業・商品となります。
また資本家たちから新たな投資を受ける事ができるようになります。これをエシカル投資といいます。
〝レジリエンス〟は、〝強靭な・しなやかな〟という意味があり、都市が災害に対応する力をつける事もレジリエンスの強化と言えます。
現代は人口増加により、アジア・アフリカ等で都市化が進み、ドバイ、中国、シンガポールなどで高層ビルの建設ラッシュが現在進行形で進んでいます。その他の発展途上国でも、ビルの建設が多くなっていく事が予測されます。
建設に必要なコンクリートには、〝砂〟が必要で、砂漠の砂は適さない為、多くが近隣諸国からの輸入で賄われています。
そのため近隣諸国では砂が失われ、砂浜や島などが消滅する〝国土の減少〟が起こっています。さらに採掘により川の砂が失われる事で水位が下がり、河川の氾濫などの被害拡大につながっているそうです。
現在世界では異常気象の他、様々な理由で災害が増えています。
災害を防ぎ、被害を軽減し、復興を早くすることは、世界のあらゆる国で必要だと考えらえます。そのためにODA(政府国際援助)による整備などは必要とされています。
また、防災技術のシェアも、今後重要になるではないでしょうか。例えば日本では、防災のための砂防工事の技術が優れています。
これは川の氾濫などによる土砂災害を防ぐための工事で、山が削られてその土砂が平野に押し寄せるという事態を防いでくれています。
こういった技術を海外に輸出することで、国際的に大きく貢献できるのではないかと思います。
不幸な事に災害が多い地域に住む人々は、貧困を伴う場合が多いと言われています。例えば水害の多い湿地帯や、竜巻や山火事が発生しやすい地域などは貧困層の人々が住んでいる傾向があります。
貧困の最中で災害に見舞われると、回復できない程のダメージを負うことになります。
その様に考えると、目標10の解決策として、目標11が繋がっていると考えられます。
最後に持続可能な都市デザインという面で先進的なデンマークの例を挙げます。〝良いパブリックデザインは、魅力的な都市をつくりだす〟と、デンマークのある建築家は言ったそうです。
〝パブリックデザイン〟とは、快適性のみならず都市の〝課題〟を複合的に解決する、イノベーションを実現するためのデザインとされています。
例に挙げると、デンマークでは公共施設として、破棄物発電施設が2017年に建設されました。この施設は、ごみを焼却する際の熱を回収し蒸気を作り、その蒸気でタービンを回すことによって発電を行う施設です。
一般的にこのような施設は市民から嫌われる迷惑施設と呼ばれ、郊外に建設されることが多いです。しかし、デンマークの施設は発想を転換し、施設の屋上を冬は人口スキー場、夏はトレッキング施設にして頂上から市街地を一望できるようになっています。
隣接してスポーツ施設がつくられて都心のスポーツリゾートになる予定になっています。
これによって廃棄物の処理、電力の供給、そして市民の健康の増進と、環境やエネルギーの教育学習など、複合的に都市が抱える問題を解決する施設となっています。
デンマークではこの他、港の水質改善を行うと共に、港の海の中にプールを建設して市民のリゾートとし、さらに地価を上げるという取り組み、そして中心部の公園に様々な国の遊具や照明などを設置し、多国籍の人々が集う交流公園としました。これによって約60ケ国におよぶ市民のコミュケーション改善、交流の促進、治安の改善、公園によるエリアの価値向上などの効果を挙げることに成功しています。
このようにデンマークではデザイン(設計)という観点で、持続可能な都市づくりを目指しています。



コメント