テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。
歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。
※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています。(なお、諸説ありでよろしくお願いいたします。)
畿内(関西)の情勢
1560年〝桶狭間合戦〟の少し前、落ち着きをみせていた京の都の情勢が大きく変化し始めます。
畿内(近畿)では将軍 義輝が摂津(大阪)の大名三好氏に追われ、近江(滋賀)に逃亡し、政治運営は三好長慶(みよしながよし)が行う状況にあったのです。


しかしながら、畿内(関西)の大名たち(六角氏、畠山氏等)の多くが将軍 義輝を支持し続けていたため、三好氏と将軍義輝の間にはかろうじて均衡が保たれていました。
この頃は、まさしく三好氏の絶頂期と言えます。
朝廷は、将軍ではない三好長慶を武士の代表と認識し、政治が行われるようになっていたのです。
そしてそのことを象徴するような出来事が起こりました。
1558年 正親町天皇(おおぎまちてんのう)の践祚(せんそ=天子の位を受け継ぐこと)によって、改元(元号を改めること)され、朝廷と三好長慶でその決定を下します。
本来室町時代で改元は、朝廷と幕府つまり天皇と将軍とで決められるのが通例でした。そのため将軍義輝は、自分の知らぬ間に改元が行われたことに危機感を募らせます。
足利将軍の京帰還
1558年 将軍義輝は近江の大名六角氏らと共に挙兵し、京の三好氏に戦いを挑みます。しかしこの戦は三好氏の勝利に終わります。そのため、将軍義輝はしぶしぶながらも改元を承認して三好氏と和解するのです。
この頃、将軍の権威を利用して三好氏の力を抑えこもうと目論む勢力がありました。
その勢力は、この機会に将軍義輝の京復帰を後押し、三好長慶はその外圧に屈する形で将軍義輝を京の都に迎え入れるのです。
義輝は京に帰還を果たしてすぐに、正親町天皇と面会したとされています。その後、復帰を祝いうために上洛した織田信長・斉藤義龍・長尾景虎等の大名たちとの面会を行います。
実のところは、織田信長は尾張の公認の支配権を得るため、長尾景虎は関東管領就任を願いでるため、斉藤義龍は家格上昇を願うことが本当の目的だったと考えられています。
この時代すでに武威を失っていたとはいえ、大義名分を得るための将軍権威に、まだ利用価値があったということです。
この頃に最も強大な力を持っていた三好長慶でさえ、外交では将軍権威を利用するようになり、将軍とはもちつもたれつの関係となっていくのです。
京に帰還した将軍義輝の下には、各地の大名から多くの献上品が届きました。
そして将軍義輝は京の住いとして〝御所〟を建設します。その建築費用は献上品で賄われたのです。
建設当時の名は〝二条御所〟でした。しかし江戸時代頃に〝初代二条城〟と呼ばれるようになります。
二条御所(初代二条城)
※図と写真はイメージです。
場所は現在の二条城の場所から少し離れたところにありました。(京都市上京区武衛陣町)現在はその跡地として〝足利義輝邸 遺址〟とされています。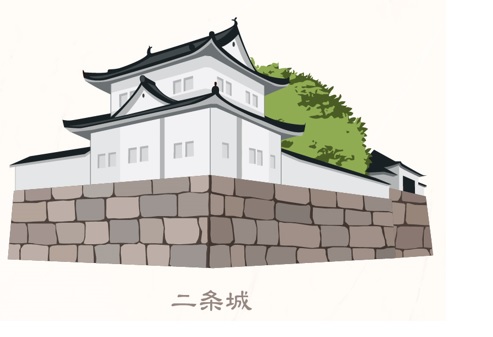
内部は豪華絢爛で、将軍義輝の部屋には、金に塗られた蓮や鳥などの障壁画が飾られ、部屋に敷かれた敷物や窓の格子などにも技巧が凝らされた最良のものが使われていたとされています。

1560年になると、二条御所には本格的で非常に深い〝堀〟が作られ、さらに石垣により城郭化されていきます。これは京で三好氏などとの、軍事的な緊張感があったのだろうと考えられます。
将軍義輝の外交政策
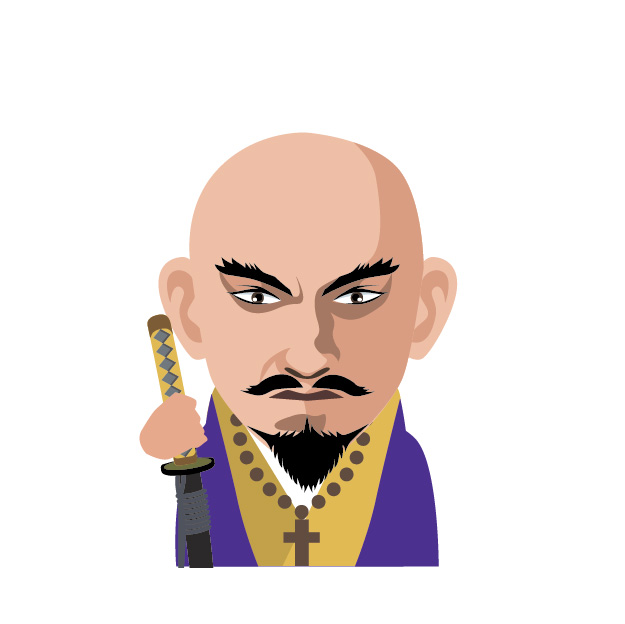
将軍義輝への献上品を見ると、まずは北九州の大友義鎮(宗麟)から大金が上納されていました。これは北九州の最大勢力大内氏(すでに没落)の後釜として、北九州の公式な支配を認めてもらう目的がありました。
大友氏はお金以外にも、南蛮貿易で得た鉄砲や模倣品(美術品として価値があった)を献上していたようです。将軍義輝はその鉄砲を各地の大名に下賜(身分の高い人がくださること)するなどして活用していたようです。
この努力は実り、大友義鎮(宗麟)には九州探題の職が任じられます。そして大友氏は九州を統治する大名として幕府に公式に認められたのです。
その一方、大友氏に隣接する安芸(広島)の毛利氏は、自領にある石見銀山〟から産出される銀を上納して、当主元就(もとなり)が陸奥守に任じられます。

さらに毛利氏は大友氏(九州)と尼子氏(山陰)に挟まれた二方面作戦の苦境を打開するため、将軍義輝を利用して停戦を成功させます。戦国大名としての政治力は、毛利氏が大友・尼子よりも一枚上手だったのです。
東北では伊達氏が熱心に上納に励みます。この当時の東北地方には守護大名が存在しませんでした。その代わり幕府から奥州探題と羽州探題が任じられていました。それが大崎氏と最上氏です。
この両氏は源氏の足利一門として家格が高く、幕府から大名扱いにされていました。その一方で、古くから東北にいた武士の多くが、国人(地方豪族)という身分の扱いでした。
伊達氏も、古く鎌倉時代から東北で勢力を築く大豪族ですが、あくまで国人(地方豪族)の身分でしかありません。
伊達氏は熱心に東北の〝みちのくの金〟や、名馬・鷹を上納したことで、念願がかない奥州探題に任じられたのです。
この出来事は源氏一門(血統)よりも経済力(力)が重視され、戦国時代を象徴しています。
長尾景虎の関東管領就任
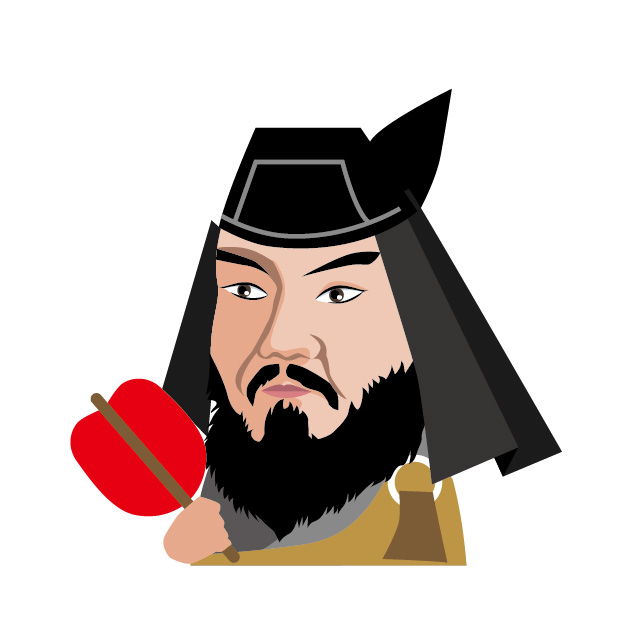
越後の大名長尾景虎(謙信)は、1560年の上洛の際に、上杉氏が世襲していた関東管領に復権させてほしいと願い出ていました。(この当時北条氏に簒奪されていた。)
そしてこの頃に、長尾姓から主家の上杉姓にあらためていました。(さらに名を景虎から政虎に変えていました。)
政虎は鎌倉時代からの足利家臣、上杉氏を守ることを将軍義輝に約束し、さらに足利氏と上杉氏が協力することで、敵対勢力に立ち向かおうと誓いあいました。
このようなことがあり、上杉政虎(謙信)は幕府の〝大義名分〟を得て意気揚々と関東に出兵するのです。
1560年 上杉政虎(謙信)は、関東管領を自称する北条氏の討伐に向かいます。
これは自身の関東管領職を正式なものとするため、そして代々慣例となっていた鎌倉の鶴岡八幡宮での拝賀式を行う目的があったようです。
鶴岡八幡宮
源氏の氏神で、鎌倉幕府の初代将軍源頼朝ゆかりの神社として関東方面で知名度が高い。

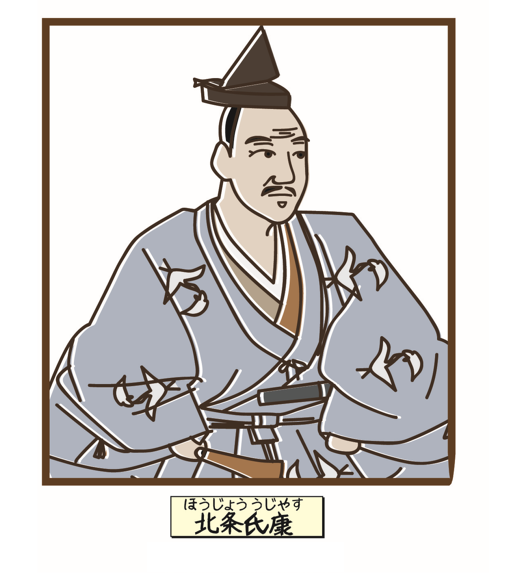
北条氏康は難攻不落小田原城に籠城し、上杉政虎(謙信)の猛攻撃を耐え忍びます。しかしこの戦では、城に入れなかった多くの民が焼き討ちに合い犠牲になりました。
民への公正な政治を身上とする北条氏康は籠城策の責任をとり、嫡男 北条氏政(ほうじょううじまさ)に当主の座を譲ったとされています。
跡を継いだ北条氏政は小田原城下町の再整備を行います。
そして長い年月をかけ城郭を拡大し、城の中に民の家や田を囲い込み、小田原城は籠城しながら食料生産を可能とする本当の難攻不落のお城へと変貌していくのです。
小田原城
神奈川県の遺跡として、史跡名勝天然記念物に指定。小田原城は関東支配の中心拠点として整備拡張され、豊臣秀吉の来攻に備え、城下を囲む総延長9kmに及ぶ総構の出現に至って、その規模は最大に達しました。
残念ながら当時の城郭は残っておらず、北条氏の滅亡後に、徳川家康の家臣・大久保氏や稲場氏によって、近世城郭に改修されて一新されています。
1923年の関東大震災により、石垣などすべて全壊しましたが、1960年に廃城以来となる市民待望の天守閣が復興されました。
決戦!川中島

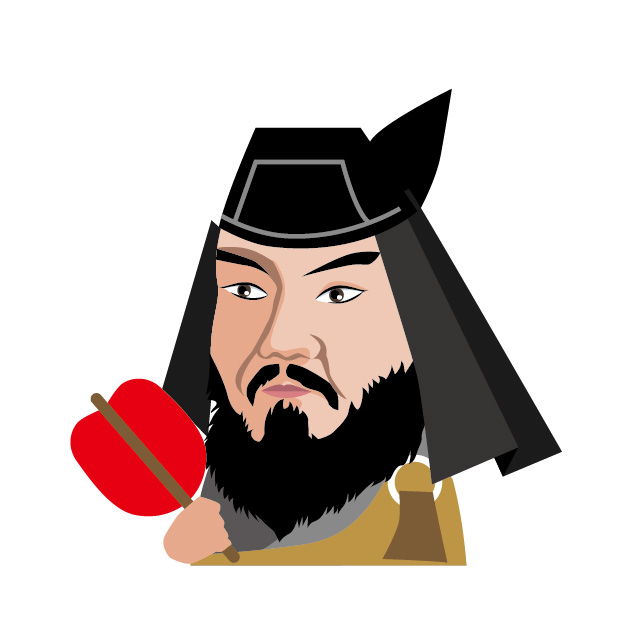
武田信玄 上杉輝虎(謙信)
この戦の最中に上杉政虎(謙信)は鶴岡八幡宮で(山内上杉家から)正式に関東管領の職を移譲されました。そして名は上杉輝虎(うえすぎてるとら)に改名しました。
そして小田原城の籠城戦中に、北条氏同盟国である武田氏が、北関東めがけて侵攻していたのです。
この武田氏の動きを察知した上杉輝虎(謙信)は、川中島まで引き返し陣を張り、侵攻していた武田氏を迎えうつ準備を整えます。
これが計5回行われた川中島の戦いでも、最も熾烈とされる第4次川中島の戦いです。
この戦いについて真偽不明な点が多いですが、一説では武田軍師 山本勘助の作戦で、別動隊による背後からの攻撃、〝キツツキ戦法〟が行われたとされています。
しかしこの作戦を見抜いた上杉輝虎(謙信)は、立ち込める霧を利用して姿を隠し、逆に武田本陣に奇襲をかけます。その結果、上杉輝虎(謙信)と武田信玄の大将同士が霧の中で邂逅し、一騎打ちが起こったという話が残っています。
川中島古戦場

この戦いでは武田氏が軍師山本勘助を始め、信玄の弟信繁(のぶしげ)が討ち死にするなど多くの被害を出しましたが、結果的に上杉軍が引き上げたため決着つかずとされています。
真の敵は足利将軍

三好長慶 重臣 松永久秀
ここで畿内(関西)に話が戻ります。
三好長慶とその重臣松永久秀は、幕府内で出世し役職と官位を得ていました。三好氏は全国の大名をはるかに越えて将軍家に次ぐ〝家格〟になっていたのでした。
このことで畿内(関西)の大名たちが不満を持ち三好氏に反発します。
1562年 河内(大阪)の畠山氏と近江の(滋賀)六角氏の共同軍が、三好氏に攻めかかります。
当主の三好長慶が畠山氏、松永久秀は六角氏を迎え討ちます。しかし強大な三好氏も両軍同時に戦う二方面作戦では、苦戦を強いられます。
三好長慶は苦戦しながらも阿波(本拠地)の援軍と合流し、畠山軍を打ち破ります。敗れた畠山氏は河内から別領の紀伊(和歌山)へ逃亡していったのです。
近江六角氏も畠山氏の敗北に合わせて撤退し、戦に勝利した三好氏は、この後松永久秀が豪族の反乱が起こっていた大和(奈良)を平定しています。
このような地方豪族との反乱は丹波方面にも広がっていきました。
これらの畿内各地で起こった反乱は、実は〝反三好勢力〟の結束によるものでした。しかし裏でこれらの勢力が〝将軍義輝と繋がっていた〟と考えられています。

ここにいたって三好長慶は、自分が将軍を利用していたつもりで、実は真の敵は将軍だったことに気が付いたのです。
三好氏の世代交代
1564年 三好氏嫡男、義興(よしおき)が若くして病で亡くなり、三好長慶の養子義継(よしつぐ)が後継者となります。
義継は長慶の弟と藤原氏九条家の間の子で、当時の日本において、武家と貴族の最高の貴種でした。
また松永久秀の子久通(ひさみち)も、松永氏の家督を譲られていました。
畿内の最大勢力の三好氏に、いよいよ世代交代の時期が訪れたのです。

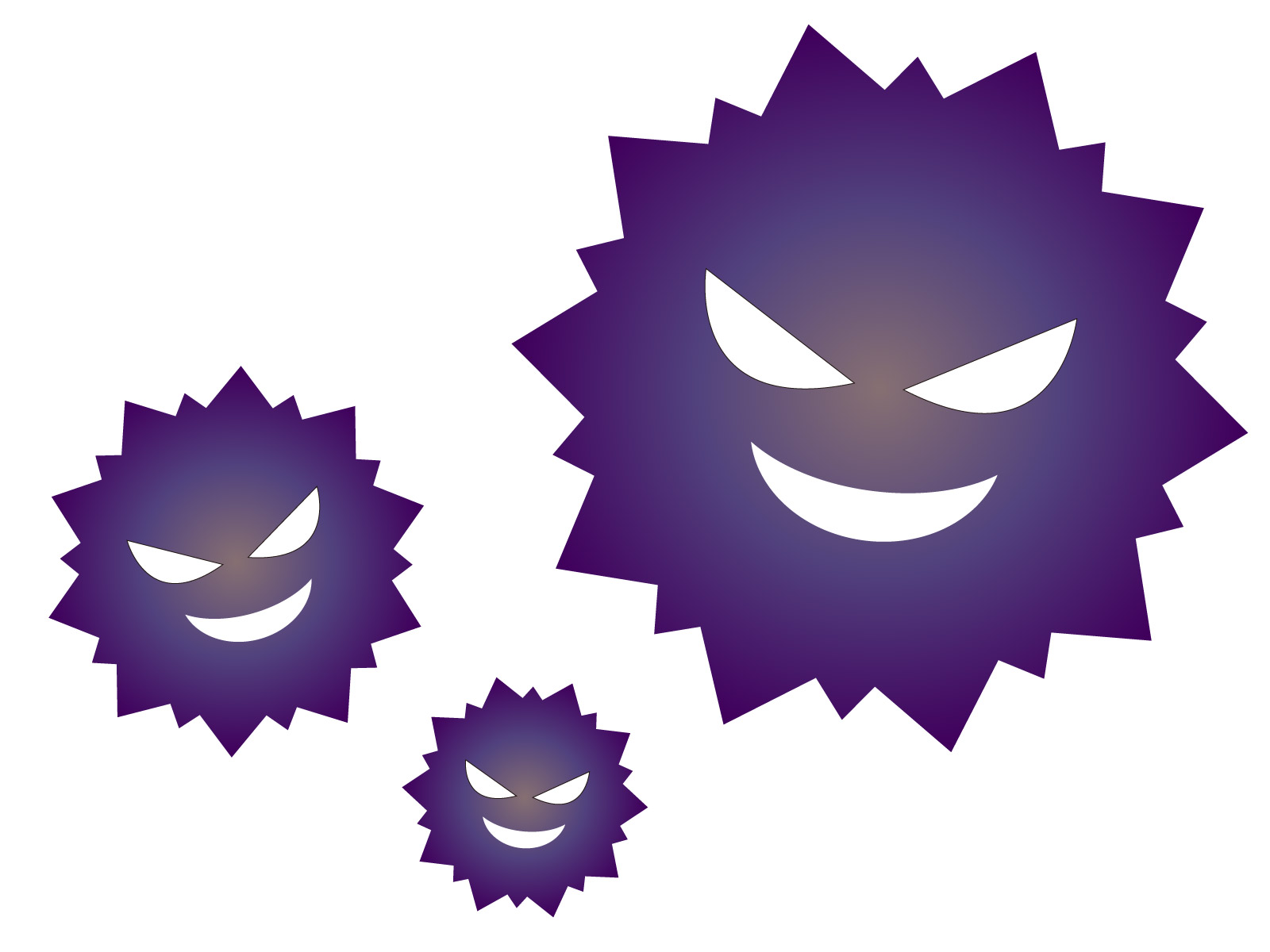
三好長慶
1564年 三好氏当主 長慶が病で亡くなります。
これは長慶が、後継者を盤石にするために弟を殺害したこと、また将軍を始め多くの敵を相手にした多大なストレスによるものではないかと考えられています。
畿内の覇者長慶の死は、安定していた畿内(関西)の情勢を大きく変えることになっていくのです。
将軍義輝の死
1565年 将軍義輝が殺害される大事件が勃発します。

首謀者は三好義継(当主)とその家臣松永久通とされています。
この時一万もの大軍を率いて京に入った三好氏に、将軍義輝はまったく警戒していなかったようです。
そして翌朝二条御所を急襲して将軍義輝とその弟と母を討ち取ったのです。三好義継はなぜ突然に凶行を行ったのかはっきりと分かっていません。
しかし今後三好氏は、自国(阿波)で庇護していた12代将軍義晴の弟、義維(よしつな)の子、義栄(よしひで)を第14代将軍として擁立していくのです。
足利義昭の逃避行
その頃、大和(奈良)の興福寺に、将軍義輝の弟の覚慶(義昭)がいました。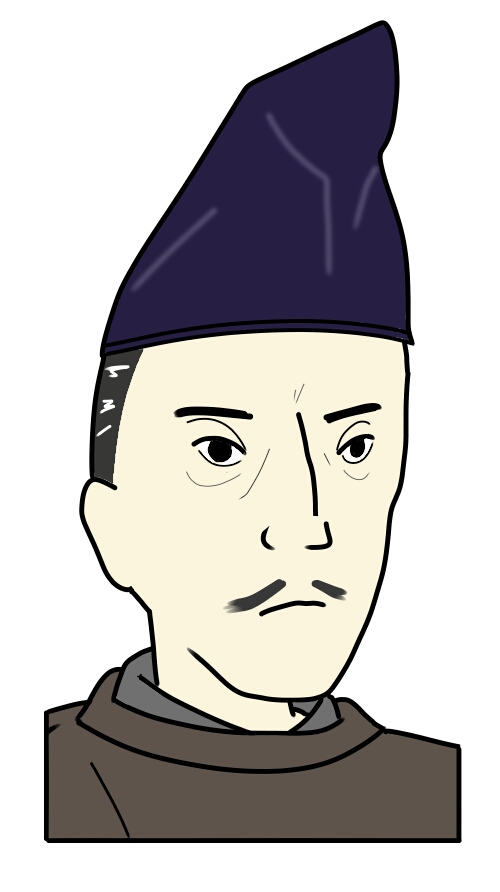
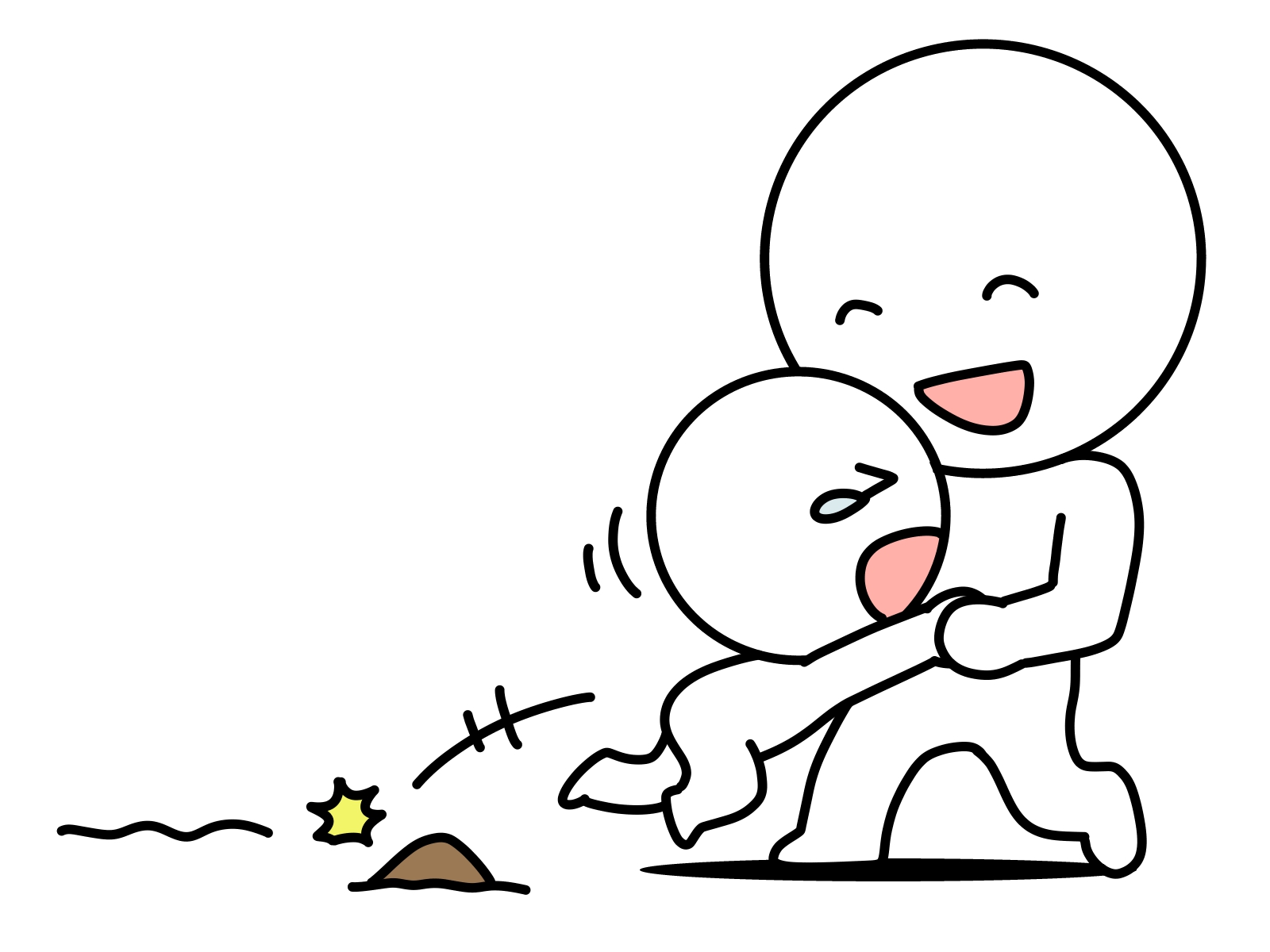

覚慶(足利義昭) 三好氏重臣 松永久秀
覚慶(義昭)は大和の松永久秀に保護されます。これは松永久秀が覚慶(義昭)を利用しようとした説があります。
しかし覚慶(義昭)は密かに大和を脱出します。逃げ出した覚慶(義昭)は後ろ盾となってくれる大名を求め全国各地に書状を送ります。
しかし近江の六角氏は三好氏と協調しており、また頼みとした織田氏と斉藤氏は互いに対立して戦中、上杉氏と武田氏も戦中だったことから、やむなく一旦上洛をあきらめます。
こうして覚慶(義昭)は、かつて十代将軍義材と同様に、越前の朝倉氏の下に逃避行に出るのです。
栄華を誇る一乗谷朝倉氏
越前にたどり着いた覚慶(義昭)は、将軍就任に向けて元服式を行います。場所は越前一乗谷です。朝倉義景の館に京から関白二条氏が招かれ、覚慶(義昭)は次期将軍として箔をつけていきます。
この時代の一乗谷の城下町はとても発展していました。敦賀の貿易港があり、足羽川の水運に恵まれ、交易は盛んで海外からも陶磁器など文化が入っていました。
また、鍋や包丁など鉄製品を製作する職人が多く、越前焼の焼き物が生産され、文化・経済活動はとても活発だったようです。
応仁の乱以降、越前は戦が少なく安全だったこともあり、京から戦乱を逃れた都人(みやこびと)を抱えて文化が発展し、公家たちとの交流も盛んだったようです。
そのため一乗谷は北陸の小京都〝北ノ京〟と呼ばれていました。
こうして足利義昭は、しばらくの間越前の朝倉義景(あさくらよしかげ)を頼りに庇護されることになります。
越前一乗谷朝倉氏遺跡
一乗谷は福井市街の東南約10kmにあり、戦国大名朝倉氏の城下町の跡が、良い状態で埋まっていました。現在は、その城下町全体が発掘されて再現されている、とても貴重な歴史遺跡として日本遺産に認定されています。
一部の朝倉氏の遺跡はそのまま残して保存されています。中でも朝倉氏遺跡の前には唐門があり、見所の一つです。

町の規模は大きく、越前侵攻で織田信長に焼き払われた際に、信長もその発展ぶりに驚き、焼き討ちを命じたとされています。
織田信長 天下を目指し動く
織田信長
尾張では桶狭間の戦いで一躍名が知られた織田信長が、密かに天下の野望を抱いていました。
これまで尾張統一のため、守護の斯波氏(足利一門)の権威を利用してきた信長は、この頃に斯波氏を追放しています。名門であっても、力のない者は消えていくのが下剋上です。
そして三河の松平元康(徳川家康)とは正式に同盟を結び、本拠地は美濃攻略に向けて、清州から小牧山城へと移していました。

1563年頃、松平家康は元康から家康に改名して、苗字も松平から徳川へと改めています。
家康は自らの血統を源氏の名門新田氏であるとしていました。
これは松平氏の始祖が得川という地域にいた、源氏新田氏の得川氏であるとする伝承が残っていたためで、家康はこの伝承を信じたのです。(なお家康の〝家〟は源氏の祖、八幡太郎源義家からとったという説があります。)
この頃の徳川家は本願寺一向一揆と戦いながら、長年今川氏に臣従して耐えてきた家臣たちと、結束の強い強力な家臣団を形成し、今川氏の支配から完全に独立して三河を支配していました。後の鉄の結束・徳川家臣団はこの頃に築かれたのです。
紀州根来寺と鉄砲
これまで織田信長は情報戦を重要視し、兵農分離によって戦闘集団を形成して、兵に6.4mもの長槍を装備させるなど、戦で様々な工夫を行っていました。
そして信長は若い頃から〝 鉄砲〟に注目していました。

信長は1554年頃からすでに鉄砲を実戦で取り入れたとされ、この頃にはすでにかなりの数の鉄砲を買い集めていたと考えられます。
鉄砲伝来(1543年)以後、種子島では刀鍛冶屋の技術力を活かし、鉄砲の自国生産に成功していました。
鉄砲は黒潮を活かした海路で種子島と交易していた紀州(和歌山)に、その生産技術と共に渡り、紀州の鍛冶職人によって大量生産が行われる様になっていました。
それを先導していたのが紀州根来寺です。
根来寺は真言宗金剛峯寺(高野山)から分かれた寺院で、この時代武装した僧兵で戦国大名なみの軍事力をもっていました。
根来寺は天台宗延暦寺や浄土真宗本願寺等と、同等の勢力を持っていたと考えられます。
根来寺
根来寺は、真言宗(しんごんしゅう)の総本山。室町時代から戦国時代にかけて大きく発展し、最盛期には寺領72万石、堂舎・伽藍2,700余があったと伝えられています。
明応5年(1496年)に建立された、日本で最も大きな木造多宝塔は〝国宝〟に指定されています。建造物や仏像などの多様な文化財が今も境内に残されています。平成17年11月 根来寺境内が、国の史跡に指定されました。
県指定文化財の大門
大門付近の愛染院は、僧兵の大将〝杉の坊〟の住坊であったと伝えられています。この人は、種子島に渡り鉄砲と火薬の製法を習い、これを伝えたとして有名です。
根来寺で鉄砲生産が行われている事を知った信長は、父 信秀から引継ぐ経済力を活かして、根来寺から鉄砲を購入していたと考えられます。
この頃鉄砲は贈答品として扱われ足利将軍家に贈られて、京の近くの近江の国友村でも生産が行われるようになり全国各地に広がっていきました。
この頃の日本には鉄砲の生産ができますが、火薬の原料がありませんでした。
原料の内の木炭と硫黄はたくさんありますが、硝石(乾燥地帯でできる結晶)が雨の多い日本に存在していなかったのです。
そのため鉄砲が戦場で活躍するようになるのはもう少し後の話になります。
織田信長の美濃攻め
この頃の織田信長は義理の父 斉藤道三の仇である、斉藤義龍との対立が続いています。
信長は桶狭間合戦後、その勢いのままに美濃攻めを行いましたが、戦果をあげることができませんでした。
しかし1561年に斉藤義龍が病で急死します。
その後継者は、わずか14歳の龍興(たつおき)です。この機を逃さず信長は美濃攻めを行いますが〝伏兵〟の奇襲を受けて敗れています。
これは斉藤義龍が残した防衛体制がしっかりしていたということでしょう。これ以降信長は、美濃の攻略のためにしばらくの年月を要することになるのです。
織田信長と武田信玄の同盟



織田信長 武田信玄
同じ頃、東国で新たな動きが起こります。武田信玄の〝飛騨侵攻〟です。
飛騨は宿敵の上杉派である三木氏がいるため、これを攻略して上杉氏に対抗しようと考えたのです。
これに合わせて動いた上杉輝虎(謙信)と、武田信玄による〝五度目の川中島の戦い〟が行われます。
これまでは北関東や信濃で、神出鬼没の戦略で上杉氏を翻弄していた武田信玄は、川中島で上杉軍と正面から対峙することになります。
守りに徹し持久戦を狙う信玄に対し、輝虎は戦果をあげることなく越後に引き返します。そして信玄と輝虎(謙信)の直接対決は、これが最後となりました。
その一方織田信長は、美濃侵攻で飛騨や信濃で武田氏と国境を隣接することに、不安を抱いていました。
そこで信長は武田氏との同盟に動き、自身の養女と信玄の子勝頼による婚姻同盟が結ばれ、信長は東からの脅威を無くすことに成功します。
駿河今川氏と甲斐武田氏の争い
この婚姻政策の成功の裏で、新たな火種が生れていました。
武田氏の同盟相手今川氏は、桶狭間合戦の後当主の今川氏真(いまがわうじざね)に対する豪族たちの反乱が起こっていました。
これを今川氏弱体の好機とした武田信玄は、越後戦略から転換して、駿河今川氏を標的に定めたのです。ついまり織田・武田の同盟によって、武田氏は今川・北条と敵対するようになったのです。
なお、この同盟に反対していた武田信玄の嫡男 義信(よしのぶ)は、謀反の罪で幽閉され、その後関係が改善することなく亡くなっています。
義信はもともと信玄と戦略で意見の違いがあったこと、今川義元の娘を妻としていたこと、さらに実母が今川派だったこと等から、親子対立が深まっていったと考えられます。
美濃の混乱 稲葉山城乗っ取り事件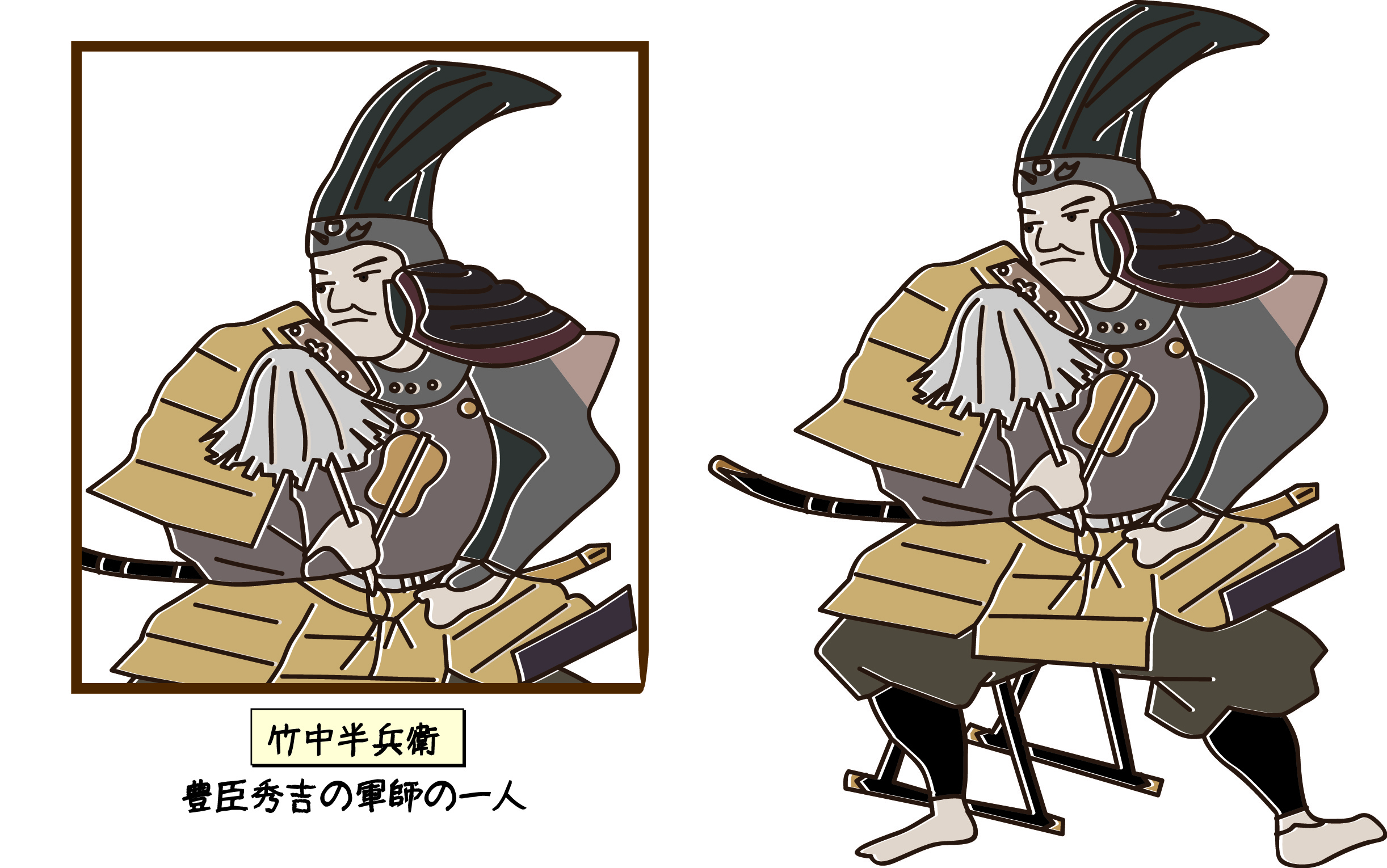
1564年 織田信長もあっと驚いたであろう〝稲葉山城乗っ取り事件〟が勃発します。これは美濃の豪族竹中半兵衛(竹中重治)によるものです。
半兵衛は若いうちからすでに多くの戦を経験していました。
父と共に本家にあたる岩手家を倒して領土を拡大し、近江六角氏の救援のため北近江の浅井氏と戦うなど、とても血気盛んな武人でした。
1562年には竹中氏の家督を継いでいたことから、織田信長との戦いでも活躍したのではとする説があります。
さて竹中半兵衛は、織田信長が苦戦していた稲葉山城をたった16人で占拠したとされています。

なぜこのような事を行ったのか、理由ははっきりしていません。
〝遊興〟にかまける主君(龍興)を諫める為、または自身を冷遇していた主君(龍興)に力を見せるける為等の説があります。
半兵衛は夜に門番を騙して城に入りこみ、隠して持ち込んだ武具を使い、龍興の佞臣(主君に媚を売る臣下)たちを切り捨てたとされています。パニックに陥った龍興は、大慌てで城から逃げ出したといいます。
それから竹中半兵衛は半年もの間政務をとり続け、その後龍興に城を明け渡して、その責任を取るように近江(滋賀)での隠遁生活に入ります。この時の半兵衛には、すでに美濃の未来が見えていたのではないでしょうか。なお竹中半兵衛はその後、織田家臣の軍師として活躍します。
稲葉山城 落城
1565年 京の将軍義輝殺害事件の影響で、膠着状態にあった美濃攻めが大きく動きます。
この頃、越前にいた足利義昭は、再び各地の大名たちに上洛に協力するよう要請していました。
なかでも本命とされていたのは、足利氏と深い関係のある上杉氏ですが、この時上杉輝虎(謙信)は、関東、信濃、加賀などでの争いのため動けませんでした。また、義昭を庇護する朝倉氏にも上洛の動きは見られませんでした。
その一方、京では三好氏が足利義栄を14代将軍にする画策を続けていたので、義昭はあせります。
この時足利義昭に、尾張の織田信長が頼りになると進言したのが、家臣の細川藤孝(ほそかわ ふじたか)と、その配下にあった明智光秀(あけちみつひで)です。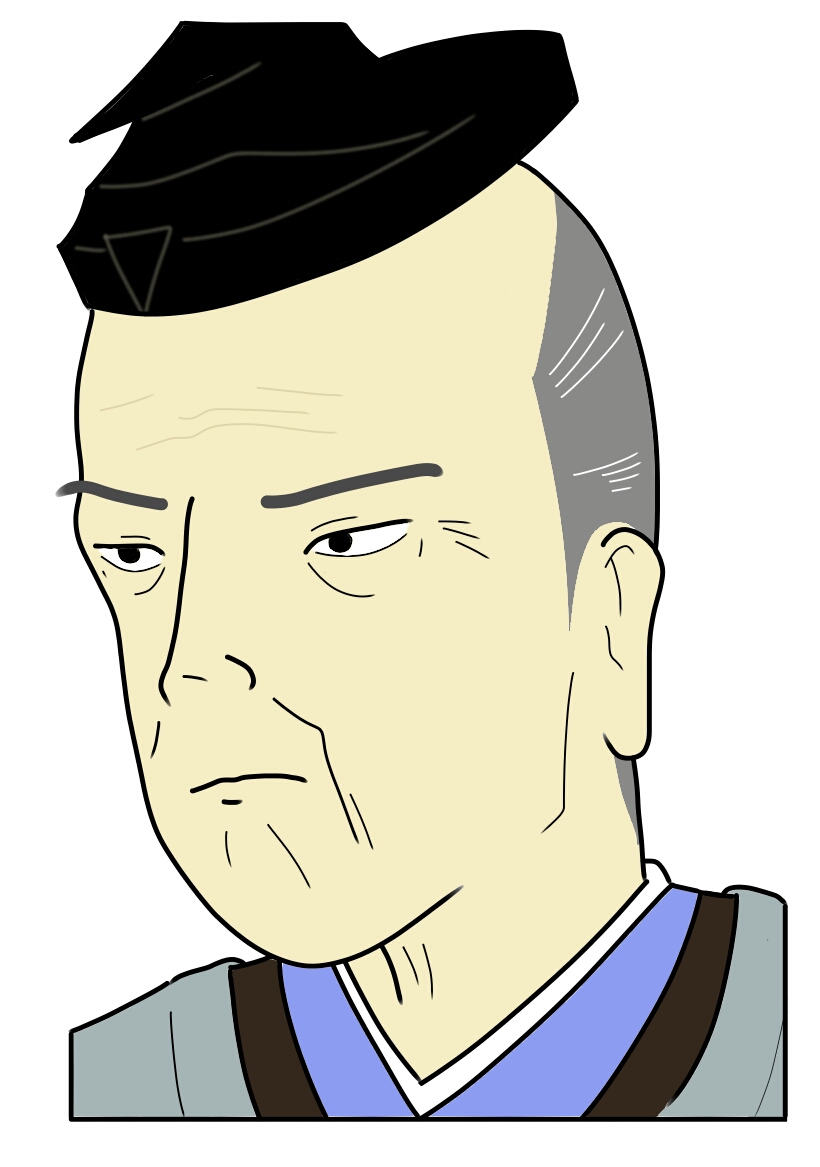
明智光秀
明智光秀は美濃守護土岐氏に仕えた一族とされています。
しかし斉藤氏が専横した美濃を離れ、越前朝倉氏のもとに身を寄せていました。そして光秀はその才覚を細川藤孝に見いだされて家臣になっていました。
明智光秀の交渉によって織田信長は、尾張・美濃・伊勢・三河の4国から兵をあげて上洛することを約束し、足利義昭と結託するのです。
美濃包囲網
織田信長が上洛する場合、美濃斉藤氏は最大の脅威となります。そのため1566年から、本格的な美濃侵攻作戦が開始されます。
しかし美濃侵攻作戦の第一歩は初戦でつまずきます。
各務ヶ原付近で行われた戦では、木曽川の氾濫で身動きが取れなくなった織田軍はあえなく撤退したとされています。
しかし翌1567年 信長は美濃攻略の前に、隣接する北伊勢(三重県桑名市・四日市辺り)の豪族とを攻略します。この戦で 滝川氏等が調略で豪族たちを降伏させたとされています。
北伊勢攻略後、美濃を包囲した信長による本格的な美濃侵攻戦が始まります。
この時信長は、三河の徳川氏、甲斐の武田氏、そして新たに北近江の浅井氏と同盟をむすび、美濃侵攻に集中する体制をつくったのです。
美濃 稲葉山城攻略
美濃侵攻戦で頭角を見せたのは、木下藤吉郎(きのしたとうきちろう)、後の豊臣秀吉です。
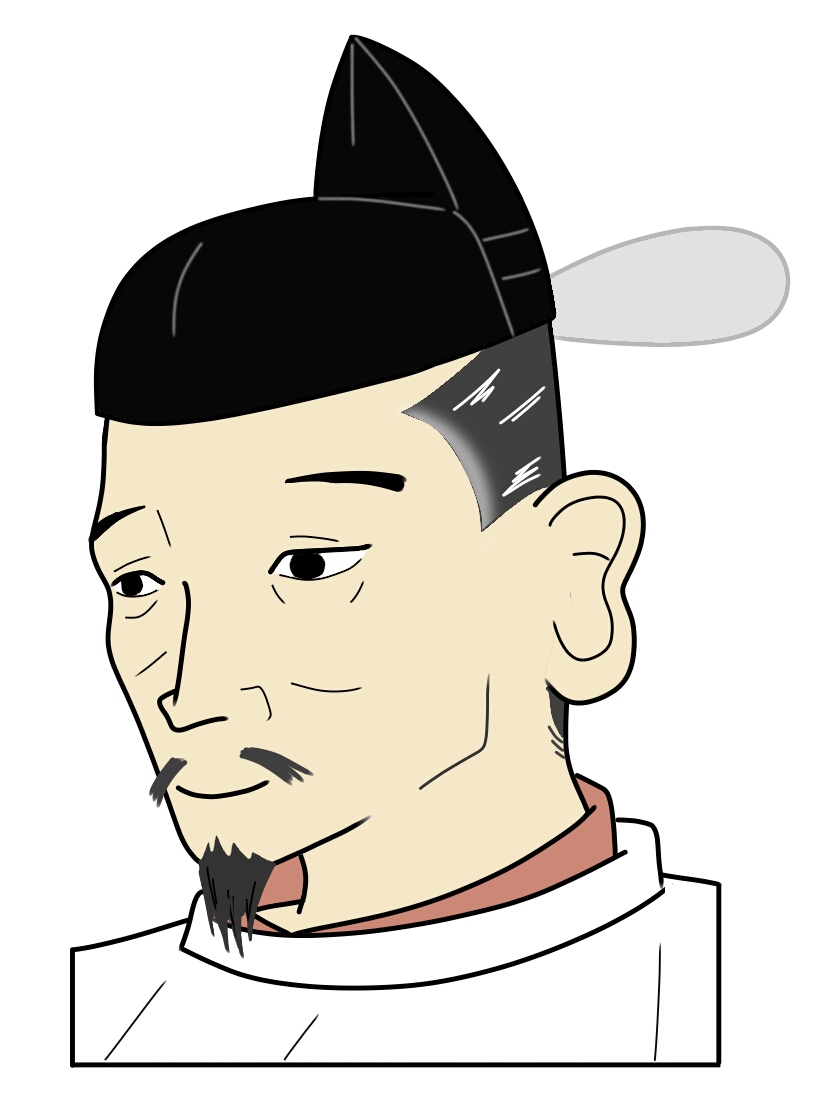
木下藤吉郎は初めは信長に仕える小姓(雑用係)でしたが、この頃にはすでに武将として隊を率いる身分になっていました。
木下藤吉郎は美濃出身の蜂須賀小六(正勝)を連れて、美濃豪族たちの調略に奔走します。
後に〝人たらし〟の異名をとるようになる木下藤吉郎と、外交折衝の才能を開花させる蜂須賀小六は、斉藤氏の主力である稲葉・安藤・氏家等を次々と降伏させていきます。
これには竹中半兵衛の〝稲葉山城乗っ取り事件〟の影響もあったと考えられます。
大切な居城を家臣に奪われる大失態で、当主の斉藤龍興の求心力が失われていたのでしょう。周囲の美濃豪族たちを離反させたことで、織田軍は電光石火で稲葉山城を攻略したのです。
織田信長は稲葉山城に入り城の名前を〝岐阜城〟と改め、この城を拠点に上洛作戦に備えます。
岐阜城の名には諸説あり、かつての美濃守護 源氏一門土岐氏の名前からとったとする説があります。
足利義昭と結託するにあたり表向き、源氏(足利将軍家)に権威を取り戻す姿勢を見せたのではないでしょうか。
岐阜城
金華山(きんかざん)山頂に位置し、岩山の上にそびえる岐阜城は、難攻不落の城としても知られ『美濃を制すものは天下を制す』と言われるほどでした。
信長公は、長良川での鵜飼観覧、「地上の楽園」と称された山麓居館など、冷徹なイメージを覆すようなおもてなしで、ルイス・フロイスら、世界の賓客をも魅了したとされています。
文化庁が平成27年度から創設した制度「日本遺産」。地域に根付き世代を超えて受け継がれている歴史的魅力にあふれた文化財群をまとめたストーリーを認定するもので、岐阜城と岐阜市はその第1号に認定されました。
信長の理想 天下布武
織田信長は岐阜城で〝天下布武〟の理想を掲げ、旗印に使用するようになります。これは一見すると自らの武威を世間に示したように見えます。
しかしこの時代の天下は、京で将軍を中心とする幕府と、朝廷の事を指していたことから、武を布く(行きわたらせる)ことによって、天下(幕府や朝廷)に権威を取り戻すという意味だったと考えられています。
この時織田信長の本心は定かではありませんが、表向き足利将軍家の復権を広く天下に示そうとしていたと考えられるのです。
次の話
10分で読める歴史と観光の繋がり 足利義昭・織田信長の連立政権誕生、仏教勢力との経済戦争/ゆかりの 茶の湯の発祥、ものづくり都市〝堺〟/西の難攻不落月山富田城/比叡山延暦寺と門前町坂本


コメント